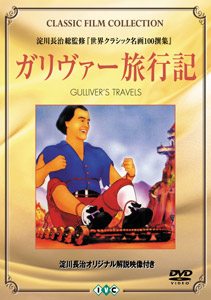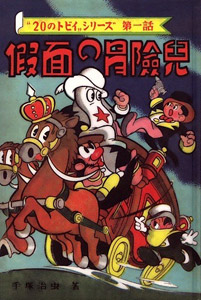手塚治虫は、アニメーションの製作に、ときにはマンガ以上の情熱を注いでいた。先ごろ公開された映画『アニメ師・杉井ギサブロー』の中では、手塚が「アニメを作ることには造物主の優越感がある」と語った映像が引用されていた。自分の描いた絵がまるで生命を吹きこまれたかのように動き出す! 幼いころ、そんなアニメの魅力にとりつかれたひとりの少年が、やがて虫プロを設立し、その夢を実現した。今回はそんな手塚少年のアニメとの出会いから、「自分もアニメを作りたい!」という夢を抱くまでの「あの日あの時」を振り返ります!
◎B・Jに登場したアニメ青年!
1978年に発表された『ブラック・ジャック』第224話「動けソロモン」は、プールでおぼれかけたピノコがアニメーターの青年に助けられるというお話だった。
青年はアニメ製作会社で動画を担当していた。青年は自分のまかされた“ソロモン”という名前のライオンを生き生きと動かしたいと、500枚の動画にして会社へ持っていった。だが社長は「これでは費用がかかりすぎて商売にならない」と言ってその動画をボツにする。
このエピソードに出てきたアニメーターの青年は、これより20年前の1958年に発表された作品『フィルムは生きている』でもアニメーターを演じていた。そしてこちらのお話も、アニメーションの製作に情熱をそそぐふたりの青年を、宮本武蔵と佐々木小次郎の巌流島の対決になぞらえて描いた熱血ストーリーだったのだ。
両作品とも、アニメへのつきせぬ思いから生まれた傑作と言えましょう。
『ブラック・ジャック』の第224話「動けソロモン」は、講談社版全集では第166巻『ブラック・ジャック』第16巻に収録されている。『フィルムは生きている』に登場する宮本武蔵のライバル、佐々木小次郎もワンカット出演しているのでご注目!
◎マンガは本妻、アニメーションは愛人
そんなマンガ執筆とアニメ製作の二足のわらじをはき続けていた手塚は、かつてインタビューなどで「自分にとってマンガとアニメは何か」と問われると、いつもこう答えていた。
「マンガは“本妻”、アニメーションは“愛人”なんです」
リードでも紹介した、アニメ監督・杉井ギサブローの半生を追ったドキュメンタリー映画『アニメ師・杉井ギサブロー』の中にも、手塚がこの言葉を語っている映像がおさめられていた。
話は脱線するけど、名前が出たのでここで杉井ギサブロー監督についてざっと紹介しておこう。
杉井ギサブローは1958年、18歳で東映動画に入社し、アニメーターとして仕事を始めた。その後1961年、手塚が立ち上げた虫プロに参加。『悟空の大冒険』『どろろ』などで異色の演出が注目された。
虫プロ倒産後、虫プロ出身の田代敦巳が立ち上げたグループタックで仕事を始めた杉井は、1980年代半ばには、あだち充原作の青春アニメ『タッチ』を総監督。このテレビアニメは社会現象ともいえる一大ブームを巻き起こした。
◎グスコーブドリの伝記がつなぐ師弟愛!
そして今年2012年7月には、杉井が監督・脚本を担当した劇場アニメ『グスコーブドリの伝記』が公開された。
同題の宮沢賢治の童話を原作としたこのアニメ映画は、もともとはグループタックが製作していた。しかしその製作のさなかに代表の田代が亡くなり、グループタックは倒産してしまった。そのため一時はお蔵入りになりかけたが、手塚プロが製作を引き継ぐことになり、無事公開にこぎつけたのだ。
手塚のもとでアニメを学んだ杉井が情熱を注いだ作品がお蔵入りになりかけた。その製作をめぐりめぐって手塚プロが引き受けた。アニメ業界は狭いとはいえ、こうした不思議な縁の根底には、亡き手塚先生の思いが働いていたとしか思えません。
ドキュメンタリー映画『アニメ師・杉井ギサブロー』のチラシ。監督はアンダーグラウンドな世界のドキュメンタリーを多く手がけてきた石岡正人。杉井はこの映画の中で手塚治虫からの影響を大いに語っており、また懐かしい手塚のインタビュー映像や虫プロのアニメ映像も満載だ。公開館が少ないので、公式サイトでチェックして、お近くで上映されていたらぜひご覧になってみてください。手塚アニメファンは必見の映画です。公式サイト→映画『アニメ師・杉井ギサブロー』公式サイト
◎アニメーションは手塚の幼なじみ!
さて、話を元に戻そう。「マンガは“本妻”、アニメーションは“愛人”」という手塚の言葉である。
ここにはマンガとアニメに対する距離感の違いや、つきあい方、お金のかかり方(笑)など、両者に対する思いがひとことでスパッと説明されている。まさに名文句と言えるだろう。
だけどここでぼくがもうひとつ付け加えさせてもらうと、この手塚の愛人であるアニメは、じつは本妻と同じくらい長いつきあいの“幼なじみ”でもあったのだ。
◎漫画映画大会でアニメ初体験
手塚がアニメを初めて見たのは小学生のころのことだという。
「大阪の朝日会館で、毎年正月に漫画映画大会をやる。それを母に連れられて正月三日に観にいくのが、わが家の恒例であった。「ポパイ」や「ベティ・ブープ」ものといっしょに、当時まだ珍しかったディズニーのカラー漫画をやっていた」(講談社版全集第383巻『手塚治虫エッセイ集1』より)
そしてそんな中で手塚はミッキーマウスとも出会った。以下、別のエッセイより。
「小学校二年生のとき、ぼくはマンガ映画大会ではじめてミッキーマウスに対面した。そしてパテー・ベビーという古めかしい家庭用映写機を父が買ってきて、フィルムの何本かを揃えたとき、そのうちの一本は『ミッキーの突進列車』であった」(講談社版全集第387巻『手塚治虫エッセイ集2』「ウォルト・ディズニー -マンガ映画の王者-」より)
ベティ・ブープを生んだフライシャー兄弟の兄、マックス・フライシャーの仕事と生涯を振り返った伝記本。著者はマックス・フライシャーの息子で映画監督のリチャード・フライシャー。リチャード・フライシャーが監督した特撮映画『ミクロの決死圏』は、手塚治虫のマンガ『吸血魔団』(1948年)と、それを元にテレビアニメ化した『鉄腕アトム』「細菌部隊の巻」(1964年)をヒントにしたとも言われていて手塚マンガとも縁がある
◎自宅アニメ劇場の思い出
この『ミッキーの突進列車』というフィルムは、当時としてはデラックスなサウンド版だったそうで、手塚はさらに別のエッセイでそのしくみについて詳しく書いている。
「これ(『ミッキーの突進列車』)にはレコードがついていて、いざ映写を始めるという時に、ワンツースリーでレコードに針をのせる。すると、画の動きの伴奏やセリフを、レコードがやってくれるのである。だんだん画と音とがずれてくるのだが、うまくしたもので、ハンドルをガシャガシャ回しながら映す手動式の機械だったから、ハンドルを適当に加減するとまた音があってくる」(講談社版全集第387巻『手塚治虫エッセイ集2』「わがアニメ狂いの記」より)
当時の映写機はひじょうに高価だったし、うっかり触ると火傷をしてしまうから、子どもには絶対に触らせてもらえなかった。
だから手塚少年も、父親が映写機を操作している様子を、尊敬と羨望のまなざしで横からジーッと観察していたのだろう。そんな手塚家の上映会の様子が目に浮かんでくるような文章だ。
◎手塚マンガが丸っこい絵になった理由
手塚治虫がアニメ技法について語ったエッセイの中に挿入したイラスト。円と曲線を基本としたクラシカルなアニメーション表現のイメージが端的に語られている(講談社版全集第387巻『手塚治虫エッセイ集』第2巻「アニメーションは“動き”を描く」より[初出は『12人の作家によるアニメーションフィルムの作り方』1980年、主婦と生活社刊])
この漫画映画大会とパテー・ベビーでのミッキーマウスとの出会い以後、手塚はあの曲線を基本とした丸っこい絵柄にたちまち魅せられていった。手塚はこの丸っこい絵柄を「ぬいぐるみスタイル」と呼んでいる。
「ぼくは、はじめ田河水泡氏と横山隆一氏のマンガに私淑していた。それがディズニーに傾倒してからというものは、俄然、このぬいぐるみスタイルを必死になって模写し修得して、とうとういまの画風になってしまった」(前出「ウォルト・ディズニー -マンガ映画の王者-」より)
手塚によれば、ディズニーに限らず当時のアニメーションがこうした丸っこい絵柄を採用していた理由は次のようなものだっという。「動きをギクシャクさせずスムーズに見せるためには、円運動を基本としたアクションが必要であり、それにはあのスタイルが、もっとも便利だからなのだ」(同エッセイより)。
◎中国初の長編アニメーションに大感激!
こうして次第に“漫画映画”に夢中になっていった手塚少年に、さらなる衝撃を与える作品が登場する。それは日中戦争のさなかの1942年(昭和17年)に日本で公開された。中国アニメ『西遊記 鐵翁公主の巻』(1941年製作)である。
これは『西遊記』の中の牛魔王のくだりをアニメーション化した73分の作品で、中国初にして東洋初の長編アニメーション作品だった。
作ったのは籟鳴(らいめい)・古蟾(こせん)・超鹿(ちょうか)の萬(はん)兄弟。彼らはこれより前の1926年に『アトリエ騒動』という中国初のアニメーション作品を作ったが、残念ながらこちらのフィルムは現存していない。
お話は火焔山へやってきた孫悟空らの一行が、牛魔王とその妻・羅刹を相手に丁々発止の妖術合戦をくりひろげるというものだ。
◎『ぼくの孫悟空』のルーツはこれ!
手塚治虫のマンガ『ぼくの孫悟空』は、雑誌『漫画王』に1952年から1959年にかけて連載された長編作品だ。これは「火焔山のたたかい」のエピソードを丸々収録した『漫画王』1954年5月号別冊付録(※画像は復刻版)
『西遊記 鐵翁公主の巻』は、手塚少年にとって相当大きなインパクトがあったようで、それから10年後に手塚が『ぼくの孫悟空』を描いた際にも、いまだにその影響から抜けきれなかったということを告白している。
「『ぼくの孫悟空』には、この『鉄扇公主』の影響がかなりつよくでています。ことに「火焔山と牛魔王」のくだりは、はらいのけようと思ってもあのアニメのイメージが心にちらついて、とうとう、ほとんどイミテーションにちかいものになってしまったくらいです」(講談社版全集第19巻『ぼくの孫悟空』第8巻あとがきより)
両者を見くらべてみると確かに『ぼくの孫悟空』のコマ運びや構図、キャラクターの造形など、随所にこのアニメーションの影響が見て取れて面白い。
◎独自の技法をきわめた東洋タッチの傑作
実際、『西遊記 鐵翁公主の巻』は当時としてはかなり画期的な作品だった。
西洋アニメの影響と思われるバタ臭いギャグが随所に散りばめられている一方で、悟空たちにせまりくる炎や風の表現には独自の工夫がある。立体感を見せながらメラメラと前後に揺れ動く炎などは、その熱気さえ感じられるほどだ。
また時代的に見ても、ディズニーが世界初のカラー長編アニメーション『白雪姫』を公開したのが1937年のことだから、それからわずか4年後ということを考えると、これはかなり驚いていいだろう。
しかもディズニーの『白雪姫』が日本で初めて公開されたのは太平洋戦争が終わって5年後の1950年のことだから、手塚少年も、この時点では『白雪姫』はまだ観ていなかったのだ。
ちなみに手塚はさらに後年、虫プロでもテレビアニメ『悟空の大冒険』(1967年、フジテレビ)を製作しているが、こちらは前の方で紹介したように杉井ギサブローが総監督を担当した。
杉井は手塚から「好きにやっていい」という言葉を得て、その通りの型破りでハチャメチャな演出を試みた。そのシュールでサイケでブッ飛んだ演出は、いま観てもかなり先を行っているものだ。
◎終戦間際に出会った幻の傑作アニメ!
『桃太郎 海の神兵』より。海軍省が全面的に協力しているだけあって、ファンタジーな映像の中で、兵器の描写が妙に生々しいのが恐ろしい。しかし右下のカット、お猿の水兵さんが草原でくつろいでいると、タンポポの綿毛が風に飛ばされてフワフワと舞っていく。その平和なシーンに一転、軍用機の爆音と落下傘降下の音声がダブる。そこでお猿の水兵さんはフッと顔を曇らせる。そんな密かな戦争批判が込められているシーンも数多い
そして手塚のアニメーションへの思いを決定的とする作品との出会いがあったのは、太平洋戦争の末期、日本が連日空襲にさらされているころだった。
タイトルは『桃太郎 海の神兵』。1945年4月12日、終戦のわずか4ヵ月前に封切られた上映時間74分のこの長編アニメーションは、当時の松竹動画研究所が、海軍省からの依頼を受けて製作した国策映画だった。
国策映画というのは、国威発揚を目的としたプロパガンダ映画のこと。つまり日本軍の戦争を正当化し、市民の戦意をあおるためにつくられた映画ということだ。
したがってお話の中には日本の戦争を賛美する表現や、逆にアメリカやイギリスなどを卑怯で野蛮な敵国としておとしめる表現が随所に出てくる。
だけど当時としてはこれはもうどうしようもないことであり、製作者たちはその限られた条件の中で、子どもたちに夢を届けようと必死になって努力している様子もうかがえる貴重な作品となっていた。
監督は戦前の1930年代から自身の動画スタジオを持って漫画映画の製作を行っていた瀬尾光世。そのほか原画/桑田良太郎、音楽/古関裕而、作詞/サトウ・ハチローなど、当時の最高のスタッフが集結していた。
しかしこの映画が封切られたのは前述したように終戦間際のことであり、日本はすでに完全な負け戦となっていた。都市部では連日激しい空襲があり、製作者たちがこの作品をもっとも観てもらいたいと願っていた子どもたちは、田舎に疎開して、すでに都会からは子どもの姿がほとんど消えていたのである。
◎アニメ映画製作を決意する!
同じく『桃太郎 海の神兵』より。里山の自然の美しさを描いた場面や、年少者や小動物を愛する場面など、敗戦直前とは思えない平和な場面も数多い。右下は捕虜となった敵国の将校たち。あくまでも卑怯で言い訳に終始するぶざまなキャラクターとして描かれている
そんな中、当時旧制中学の学生だった手塚は、勤労動員の工場を休んで大阪・道頓堀の映画館へ行き、この映画を観た。以下、エッセイからの引用。
「ぼくは焼け残った松竹座の、ひえびえとした客席でこれを観た。観ていて泣けてしょうがなかった。感激のあまり涙が出てしまったのである。前編に
「おれは漫画映画をつくるぞ」
と、ぼくは誓った。
「一生に一本でもいい。どんなに苦労したって、おれの漫画映画をつくって、この感激を子供たちに伝えてやる」」(講談社版全集第383巻『手塚治虫エッセイ集1』より)
手塚のアニメ製作への思いが決定的となった瞬間だった。
ちなみにこの『桃太郎 海の神兵』のフィルムは戦後、占領軍によって焼却され幻のフィルムになっていたと思われていた。ところが1982年、松竹の倉庫でネガが見つかり、37年ぶりに劇場公開されたのである。
その後、テレビで放送されたりビデオソフト化もされているが、DVDソフトにはなっておらず現在は絶版となっている。貴重な文化遺産として、ソフト化していつでも観られる状態にしていただきたい。
◎アニメーターに押しかけ志願! だが……
フライシャー兄弟の
『ガリヴァー旅行記』は現在DVDソフトで観ることができる。このIVC版は映画評論家・淀川長治氏の映像解説入りだ
(発売元:アイ・ヴィー・シー 定価:(税込):3675円)
戦争が終わると、有言実行の男・手塚治虫はただちに行動を起こした。芦田巌という、当時数少ないマンガ映画スタジオを持つアニメ作家のもとを訪ね、弟子入りを志願したのだ。以下、手塚の文章から。
「昭和二十一年に上京した際、ふらりとあるマンガ映画プロダクションへ飛び込んで「僕を使って下さい」と執拗に頼み込んだ。
「だめだ、君は映画に向かん」と所長は、私の作品を見ていった。
「実力がありませんか?」がっかりしてきくと、
「一度、出版界の味をしめてしまうと、報酬その他、割りがいいもんだから、ケタ違いに不利な動画などは、とても作る気になれないよ」
「縁の下の力持ちで何でもやります。やとって下さい」
「あきらめるんだな」
私はがっかりして、以後、マンガ映画をつくることなど、すっかり忘れてしまった」(『東京新聞』「私の人生劇場」昭和42年11月3日[山口且訓・渡辺泰共著『日本アニメーション映画史』1977年有文社刊]より孫引用)
昭和21年(1946年)といえば、手塚の出世作となった『新寶島』(1946年1月、育英出版)が刊行される直前である。もしもこのとき芦田が手塚をアニメーターとして採用していたら……後のマンガ家・手塚治虫は存在していなかったかも知れない!?
◎届かないアニメへのラブレター
と、それはともかく、ここでアニメ作家への夢をいったん断ち切られた手塚は、やむなく(?)マンガに打ちこむことになる。
しかし、当然のことながらアニメへの思いを完全に忘れてしまうことはできなかった。しかもこのころは、戦争でずっと輸入されていなかった戦前のアニメーションが日本に続々と入ってきており、また新作アニメーションなど、海外の優れた作品が山のように公開されていたのだ。
もともとマンガの中に世相を引用するのが大好きな手塚先生だ。それが片想いの相手のアニメとなればなおさらだ。
手塚はあるアニメを見ては、すぐそれに感化され、そのギャグをマンガの中に取り込んだ。またほかの作品を見て感激しては、その動きを再生するようにマンガ化した。
いわばこの時期の手塚マンガというのは、アニメへの断ちがたい恋心(しかも片想いの!)を描いた、決して相手に届かない、悲しい悲しいラブレターなのである!
◎戦後のアニメ体験が手塚マンガを育てた
その一例をあげてみよう。1948年7月、手塚は『假面の冒險兒』というヨーロッパ童話調の冒険活劇マンガを発表している。
そしてこの作品を描く直前、手塚は出版社の社長から「もう少し子どもマンガ風の絵で描いてもらいたい」という注文を受けていた。
しかし……そうは言われたものの、子どもマンガ風の絵とはどのようなものなのか。悩んだ手塚がヒントをつかんだのが、ちょうどこの年の4月に公開されたアニメーション映画『ガリヴァー旅行記』を観たときだった。
『ガリヴァー旅行記』は、『ポパイ』や『ベティ・ブープ』で知られるフライシャー兄弟が1939年に発表した作品だが、戦争のため日本ではずっと公開されていなかったのだ。
「『ガリヴァー旅行記』の小人達のコロコロしたキャラクターは、たしかに劇画ふうになりかかっていたぼくの人物たちに、あるヒントをあたえてくれたのだと思います」。(講談社版手塚治虫全集第173巻『珍アラビアンナイト』あとがきより)。
こうして『假面の冒險兒』は刊行された。この作品にはフック伯爵の手下として3人組の探偵が出てくるが、これは『ガリヴァー旅行記』のボンボ国の3人組スパイへのリスペクトだろう。
『假面の冒險兒』は1948年、大阪の東光堂から描き下ろし単行本として刊行された。講談社版全集では第324巻『拳銃天使』に収録されている。また、昨年2011年に小学館クリエイティブから刊行された『手塚治虫初期名作完全復刻版BOX(2)』には、当時の装丁のままの単行本として復刻されたものが収録されている。※図版は復刻版
◎ソ連の名作アニメを70〜80回も観る!
『せむしの仔馬』は現在は『イワンと仔馬』と改題されてDVDリリースされている。これは三鷹の森ジブリ美術館ライブラリーシリーズの1本として発行されているもの。1948年のソ連製短編アニメ『灰色首の野がも』が同時収録されている
またその翌年の1949年3月には、当時のソビエト連邦で製作された、ソ連初のカラー長編セルアニメーション映画『せむしの仔馬』(1947年製作)が公開されている。
監督はロシアアニメーションの父といわれたイワン・イワノフ=ワノー。ロシアの昔話を題材にしたこの物語は、グズでのろまで兄からもバカにされていたイワン少年が、ある日、不思議な白馬と出会い、せむしの仔馬をもらったところから始まる。その仔馬は超能力を持っており、イワン少年はその仔馬の助けを借りることで王様に重用され、やがて立派な王子へと成長してゆくのである。
手塚はこのアニメーションにも大いにハマり映画館へ通い詰めた。エッセイの中ではこのアニメを「大阪や神戸で七、八十回は見た」と語っている。
そして手塚は、翌年1月に刊行された『ファウスト』の中で、さっそくこのアニメを引用している。
『ファウスト』は言うまでもなく、同題のゲーテの戯曲を手塚が自分流にマンガ化したものだけど、その基本設定を大きく外れ、展開の随所に『せむしの仔馬』の影響が見られる。
王様がファウストに次から次へと無理難題を要求し、最後には美の女神ヘレネを連れてこいと命じる。ファウストは苦労しつつメフィストの力を借りてヘレネを連れ帰る。すると王様はそのヘレネに恋をしてしまい求婚をするのだが……というこの流れは、ファウストをイワンに、メフィストを仔馬に置きかえれば、まさに『せむしの仔馬』そのものなのである。
また両作品には絵柄にも共通する部分が多々ある。手塚マンガの発想のルーツに興味のある方は、ぜひ両者を見くらべてみていただきたい。
雑誌『COM』版『火の鳥・黎明編』第1話の冒頭シーン。ウラジが火の鳥を捕えようとする場面は、『せむしの仔馬』でイワンが火の鳥を捕えようとする場面をかなり意識していると思われる。講談社版全集では第201巻『火の鳥』第1巻に収録
◎『バンビ』との出会い!
そしてさらに翌1951年、手塚は彼にとっての運命の作品ともいえるアニメーションと出会う。ディズニーの『バンビ』である。
この『バンビ』との出会いが、手塚の一度はあきらめかけたアニメーション製作への情熱をふたたび火をともした。そしてその火はやがて虫プロダクション設立となって実を結ぶんだけど……。
ここから先もまだまだ道のりは平坦ではなくて山あり谷ありだったわけであり、その話はまた稿をあらためることにしよう。
今回も長文をお読みくださいましてありがとうございます。ぜひまた次回のコラムにもおつきあいくださいね〜〜〜〜っ!!
(C)2012「アニメ師・杉井ギサブロー」製作委員会
(C)2012「グスコーブドリの伝記」製作委員会/ますむらひろし
黒沢哲哉
1957年東京生まれ。マンガ原作家、フリーライター。手塚マンガとの出会いは『鉄腕アトム』。以来40数年にわたり昭和のマンガと駄菓子屋おもちゃを収集。昭和レトロ関連の単行本や記事等を多数手がける。手塚治虫ファンクラブ(第1期)会員番号364番
コラム バックナンバー
虫さんぽ
- 虫さんぽ 第61回:夏の関西さんぽ(後編)エキゾチックタウン神戸でポートピア‘81の思い出をたどる!
- 虫さんぽ 第60回:夏の関西さんぽ(中編)京の都で手塚先生のスタミナグルメと思い出話を堪能!!
- 虫さんぽ 第59回:夏の関西さんぽ(前編)宝塚の最新手塚事情を訪ね歩く!!
- 虫さんぽ 第58回:銀座-日比谷-皇居周辺、手塚治虫大人マンガさんぽ!!
- 虫さんぽ 第57回:山手線・中央線界隈 東京都内悪のアジトとヒーローの足跡
- 虫さんぽ 第56回:冬の神奈川県・横浜でB・J&サンダーマスク、恋の思い出にひたる!!
- 虫さんぽ 第55回:北海道さんぽ(後編)旭川へアトムと火の鳥に会いに行こう!!
- 虫さんぽ 第54回:北海道さんぽ(中編)シュマリとB・Jの作品風景を求めて札幌を歩く!!
- 虫さんぽ 第53回:北海道さんぽ(前編)昭和新山とカルデラ湖に大自然の驚異を見た!!
- 虫さんぽ 第52回:春の港ヨコハマでブルアちゃんの面影をたどる!!
- 虫さんぽ 第51回:鎌倉界隈 早春の風を浴びて手塚マンガにまつわる歴史と伝統を歩く!!
- 虫さんぽ 第50回:東京 羽田空港から赤坂へ、手塚先生推薦の本格中国料理に舌鼓!!
- 虫さんぽ 第49回:再訪・福島県会津地方(後編):会津に遺された手塚治虫の宝物を巡る旅!!
- 虫さんぽ 第48回:再訪・福島県会津地方(前編):手塚治虫双六ラリーさんぽ!!
- 虫さんぽ 第47回:東京−神奈川、怪奇マンガ『バンパイヤ』の名場面を歩く!!
- 虫さんぽ 第46回:東京の東側、昭和レトロな街並みに手塚マンガの面影を訪ねる!!
- 虫さんぽ 第45回:東京・上野パート2 美術館と博物館をめぐる早春の虫ツアー!!
- 虫さんぽ 第44回:東京・上野 かっぱ寺と手塚マンガに描かれた西郷さんにご挨拶!!
- 虫さんぽ 第43回:沖縄さんぽ(後編)祭りの“跡”と手塚マンガに描かれた青い海、輝く自然を訪ねる!!
- 虫さんぽ 第42回:沖縄さんぽ(中編)手塚マンガに描かれた米軍基地の町を歩く!!
- 虫さんぽ 第41回:沖縄さんぽ(前編)手塚マンガの戦争を振り返りつつ沖縄戦跡を訪ねる!!
- 虫さんぽ 第40回:東京・新宿界隈 SF作家仲間との交流、そして路地裏アラベスク!!
- 虫さんぽ 第39回:東京・池袋界隈 手塚先生とマンガ家仲間との交流の足跡をたどる!!
- 虫さんぽ 第38回:宝塚さんぽ(後編)手塚治虫先生の実弟・浩さんと昆虫採集の森を歩く!!
- 虫さんぽ 第37回:宝塚さんぽ(前編)手塚治虫記念館で隠れキャラを探そう!!
- 虫さんぽ 第36回:大阪さんぽ(後編)マンガとアニメ、手塚先生の創作活動のルーツを訪ねる!!
- 虫さんぽ 第35回:大阪さんぽ(前編)手塚少年に芽生えた科学する心を訪ね歩く!!
- 虫さんぽ 第34回:東京・銀座から丸の内へ 手塚先生のおもてなしメニューを堪能する!!
- 虫さんぽ 第33回:東京豊島区 トキワ荘通りを鈴木伸一先生と再訪する!!
- 虫さんぽ 第32回:茨城県石岡市 火の鳥に願をかけ、江戸時代に思いをはせる!!
- 虫さんぽ 第31回:手塚先生のベレー帽をめぐって東京・銀座を歩く!!
- 虫さんぽ 第30回:東京・総武線沿線、手塚マンガゆかりの出版社を各駅停車散歩!!
- 虫さんぽ 第29回:埼玉県新座市パート2:手塚治虫の愛した緑豊かな新座の杜を散策するっ!!
- 虫さんぽ 第28回:埼玉県新座市パート1:初夏の手塚プロ新座スタジオ界隈を歩く!!
- 虫さんぽ 第27回:東京・青山から六本木へ、手塚先生、文化交流の足跡を歩く!!
- 虫さんぽ 第26回:東京・有楽町日比谷界隈。手塚アニメの原点と最晩年の手塚先生の素顔を訪ねる!!
- 虫さんぽ 第25回:手塚先生の第2の仕事場!? 東京都内・カンヅメ旅館をめぐる!!
- 虫さんぽ 第24回:音羽〜早稲田 手塚マンガの出版と収集、その歴史を歩く!
- 虫さんぽ 第23回:東京湾岸 アトム風車と羽田の大鳥居を見に行こう!!
- 虫さんぽ 第22回:東京都文京区~千代田区 陽だまりの樹さんぽ!
- 虫さんぽ 第21回:東京都新宿区・高田馬場、手塚グルメを味わう春のお花見さんぽ!!
- 虫さんぽ 第20回:神奈川県・川崎市縦断、ドラえもんと笑いの像に会いに行く!
- 虫さんぽ 第19回:東京・井の頭公園界隈:“赤いネコ”の武蔵野と昆虫館を訪ねる
- 虫さんぽ 第18回:新宿区四谷・ついに判明した手塚先生の下宿跡を再訪する!
- 虫さんぽ 第17回:【夏休み関西さんぽ・後編】兵庫県宝塚市:手塚治虫記念館周辺を歩く
- 虫さんぽ 第16回:【夏休み関西さんぽ・前編】大阪界隈:医大生時代の手塚先生の足跡を歩く!
- 虫さんぽ 第15回:東京・豊島区雑司が谷・並木ハウス周辺を歩く
- 虫さんぽ 第14回:東京・文京区と四ッ谷で手塚先生、東京進出の足跡をたどる
- 虫さんぽ 第13回:福島県会津若松(後編)・東北の城下町に手塚先生の素顔を見た!
- 虫さんぽ 第12回:神奈川県鎌倉・河童と大イチョウとフクちゃんに会いに行こう!
- 虫さんぽ 第11回:福島県会津若松(前編)・スリル博士と歩く初夏の会津
- 虫さんぽ 第10回:東京銀座界隈で、手塚先生のONとOFFの足跡をたどる
- 虫さんぽ 第9回:東京都葛飾区・柴又帝釈天(たいしゃくてん)界隈で手塚先生の足跡をたどる!!
- 虫さんぽ 第8回:練馬区富士見台・虫プロ界隈を石津嵐さんと歩く!!
- 虫さんぽ 第7回:杉並区荻窪・手塚ファン大会のルーツを訪ねる!!の巻
- 虫さんぽ 第6回:埼玉県飯能市・鉄腕アトム像周辺(後編)
- 虫さんぽ 第5回:埼玉県飯能市・鉄腕アトム像周辺(前編)
- 虫さんぽ 第4回:豊島区南長崎 元トキワ荘周辺・その2
- 虫さんぽ 番外編:江戸東京博物館『手塚治虫展』と両国・浅草界隈
- 虫さんぽ 第3回:豊島区南長崎 元トキワ荘周辺・その1
- 虫さんぽ 第2回:高田馬場・その2
- 虫さんぽ 第1回:高田馬場・その1
あの日あの時
- 手塚マンガ あの日あの時 第59回:第1回手塚治虫ファン大会が開催されるまで
- 手塚マンガ あの日あの時 第58回:あんなネタこんなネタ、小ネタコレクション!!
- 手塚マンガ あの日あの時 第57回:追跡ルポ! 手塚治虫書店を巡る7日間の旅!!
- 手塚マンガ あの日あの時 第56回:手塚治虫の描いた未来のロボット社会(その1)アトムと恋愛はできるか!?
- 手塚マンガ あの日あの時 第55回:埋もれた手塚資料に光を当てる、おもしろレーベルの挑戦!!
- 手塚マンガ あの日あの時 第54回:大公開『カラー完全版 ふしぎな少年』のできるまで!!
- 手塚マンガ あの日あの時 第53回:手塚マンガ出版の新しいカタチ、“原画コラージュ方式”に迫る!!
- 手塚マンガ あの日あの時 第52回:手塚流ジュブナイルロマンスを読む!!
- 手塚マンガ あの日あの時 第51回:怪優ヒゲオヤジの魅力に迫る!!
- 手塚マンガ あの日あの時 第50回:大長編『火の鳥』の誕生と幻の結末に迫る!!
- 手塚マンガ あの日あの時 第49回:大長編『火の鳥』の読み方ナビ
- 手塚マンガ あの日あの時 第48回:手塚マンガの音楽表現を斬るっ!!
- 手塚マンガ あの日あの時 第47回:手塚マンガのワン・ニャン戦争!?
- 手塚マンガ あの日あの時 第46回:手塚治虫のグルメマンガ・メシマズ編!!
- 手塚マンガ あの日あの時 第45回:グルメな手塚マンガ、ア・ラ・カルト!!
- 手塚マンガ あの日あの時 第44回:あるスクラップ帳で振り返る虫プロ倒産騒動のころ
- 手塚マンガ あの日あの時 第43回:もう戦争は沢山だ。半自伝的戦争マンガの誕生
- 手塚マンガ あの日あの時 第42回:二度と戦争なんか起こすまい。手塚マンガが描いた“戦後”の“戦争”
- 手塚マンガ あの日あの時 第41回:今日から君もマンガ家だ!? 手塚治虫のマンガ家入門書大全!!
- 手塚マンガ あの日あの時 第40回:変身こそが我がマンガ!? 手塚マンガのメタモルフォーゼを読む!!
- 手塚マンガ あの日あの時 第39回:人か獣か!? 手塚マンガの人外ヒロイン&ヒーローを読む!!
- 手塚マンガ あの日あの時 第38回:手塚マンガ・復刻の源流を探る!!
- 手塚マンガ あの日あの時 第37回:手塚マンガ復刻の現場を探訪する!!
- 手塚マンガ あの日あの時 第36回:手塚治虫の原作付きマンガを読む!!
- 手塚マンガ あの日あの時 第35回:人、人、人がいっぱい! 手塚マンガ・モブシーンの秘密!!
- 手塚マンガ あの日あの時 第34回:ユルくない!? 手塚流“マスコットキャラ”変遷史!!
- 手塚マンガ あの日あの時 第33回:手塚マンガで振り返る手塚治虫の生涯!!
- 手塚マンガ あの日あの時 第32回:手塚治虫の業界マンガを読む!!
- 手塚マンガ あの日あの時 第31回:マンガ家&編集者、今昔物語!!
- 手塚マンガ あの日あの時 第30回:手塚マンガの中の“中二病”を読む!!
- 手塚マンガ あの日あの時 第29回:手塚治虫ファンクラブ創立の時代!!
- 手塚マンガ あの日あの時 第28回:手塚キャラに秘められた“時代”をあばく!!
- 手塚マンガ あの日あの時 第27回:妖怪ブームの荒波に挑んだ『どろろ』の挑戦!!
- 手塚マンガ あの日あの時 第26回:手塚萌えの異色作『プライム・ローズ』の時代!!
- 手塚マンガ あの日あの時 第25回:ファン感涙! 手塚治虫全集刊行のころ!!
- 手塚マンガ あの日あの時 第24回:手塚治虫、アニメにかけた情熱のルーツを探る!!
- 手塚マンガ あの日あの時 第23回:手塚流巨大SFヒーロー誕生の時代
- 手塚マンガ あの日あの時 第22回:逆引き版『陽だまりの樹』創作秘話!!
- 手塚マンガ あの日あの時 第21回:手塚マンガのロボット年代記(後編)
- 手塚マンガ あの日あの時 第20回:手塚マンガのロボット年代記(前編)
- 手塚マンガ あの日あの時 第19回:手塚流作品タイトルの付け方(後編)
- 手塚マンガ あの日あの時 第18回:手塚流作品タイトルの付け方(前編)
- 手塚マンガ あの日あの時 第17回:手塚流青年マンガの軌跡を追え!
- 手塚マンガ あの日あの時 第16回:文明礼賛と自然回帰のはざま
- 手塚マンガ あの日あの時 第15回:大阪赤本と秘境探検ブームの時代
- 手塚マンガ あの日あの時 第14回:『マグマ大使』と特撮怪獣ブームの時代
- 手塚マンガ あの日あの時 第13回:もうひとつのW3(ワンダースリー)
- 手塚マンガ あの日あの時 第12回:『三つ目がとおる』誕生
- 手塚マンガ あの日あの時 第11回:ハレンチマンガ旋風の中で
- 手塚マンガ あの日あの時 第10回:手塚マンガが悪書だった時代
- 手塚マンガ あの日あの時 第9回:虫プロ誕生とテレビアニメ時代の夜明け
- 手塚マンガ あの日あの時 第8回:地上最大のロボットとアトム貯金箱
- 手塚マンガ あの日あの時 第7回:アトムの予言─高度経済成長のその先へ─
- 手塚マンガ あの日あの時 第6回:アトム誕生の時代─焼け跡の中で─
- 手塚マンガ あの日あの時 第4回(2):“悪魔のような男”はこうして生まれた -バンパイヤからMWへ-
- 手塚マンガ あの日あの時 第4回(1):“悪魔のような男”はこうして生まれた -バンパイヤからMWへ-
- 手塚マンガ あの日あの時 第3回:アポロ月着陸と月の石(その2)
- 手塚マンガ あの日あの時 第2回:アポロ月着陸と月の石(その1)
- 手塚マンガ あの日あの時 第1回:B・Jとミグ25亡命事件