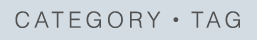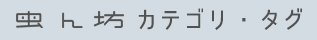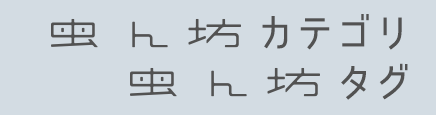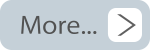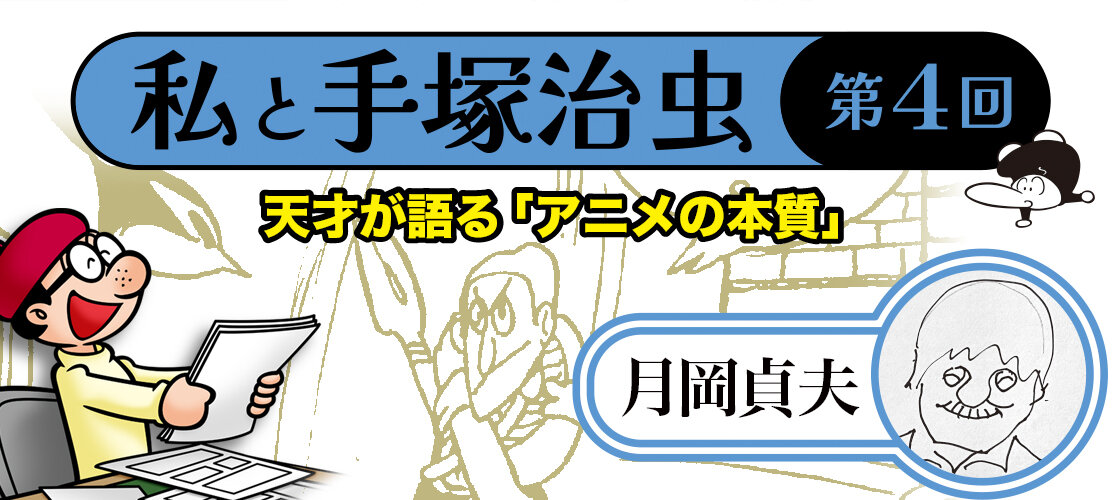
関係者インタビュー
私と手塚治虫 月岡貞夫編
第4回 天才が語る「アニメの本質」
文/山崎潤子
関係者に話を聞き、さまざまな角度から手塚治虫の素顔を探っていこうという企画です。今回はアニメーション作家の月岡貞夫さん。「天才アニメーター」と呼ばれた月岡さんは、日本アニメ界のレジェンド的存在です。手塚治虫とのエピソードから、現在のアニメ界の考察まで、さまざまな視点でお話を伺いました。
PROFILE
月岡貞夫(つきおか・さだお)
アニメーション作家。1939年新潟県生まれ。手塚治虫のアシスタントを経て東映動画入社。『西遊記』(1960年)、『ねずみの嫁入り』(1961年)、『わんぱく王子の大蛇退治』(1963年)に携わり、24歳にして東映のテレビアニメシリーズ第1作となる『狼少年ケン』(1963年)の総監督を務める。その後フリーとなり、NHKみんなのうた「北風小僧の寒太郎」(1974年)、CMの富士通のタッチおじさん、明治うがい薬のカバくんなど、多くの作品で知られる。虫プロ作品では『W3』『悟空の大冒険』『リボンの騎士』などに携わる。第45回日本アカデミー賞協会特別賞を受賞。中国美術大学、西安美術大学、北京電影大学客座教授。
◾️アニメの醍醐味は「芝居」にある
──月岡さんがマンガよりアニメのほうに面白みを感じたのは、どんなところでしょう。
マンガのコマというのは静止画でしょう。紙芝居のようなもので、絵と吹き出しがあればお話がわかる。お芝居の入る余地があまりないんですよね。対してアニメーションの本質は動くこと。動かないはずの絵が動いて、登場人物が芝居をすることに、醍醐味があるんです。
芝居という意味では、本物の役者がやる実写でもいいのですが、生身の人間の芝居では、子どもたちにはわかりにくい。でも、線描きのキャラクターが笑ったり泣いたりすると、セリフなどなくても、子どもたちは一瞬で理解できる。表現力という意味で、アニメはやっぱり抜きん出ていると思います。
──たしかに!
文学の大きなテーマに「嫉妬」があります。文学に限らず、これはコンプレックスからくる物語に欠かせない要素なんです。デュマ・ペールやシェイクスピアだってそうでしょう。
コンプレックスは妬み嫉み、いじめ、忖度として現れる。これを言葉で表現しても面白くはない。そういったものを言葉に頼らず表そうとするのは、表現者としてとても楽しいし、面白いことですよね。
たとえばロシアの古いアニメーションに『雪の女王』(1957年)というのがあるんですが、芝居が非常にすばらしくて、泣かせるシーンがあります。
あるいはポール・グリモーの『やぶにらみの暴君』(1952年)。王様の陰険な芝居が、とにかくいいんですよ。権力者には裏表がある、そうでなきゃ王様にはなれない。そういうリアルをうまく表現しているんですね。昔から、自分もアニメーションであんな芝居させてみたいと思いながら、観ていました。
──アニメなら、自分で芝居をさせて表現できるわけですね。
ただ、今の日本のアニメはそういうものをセリフで説明してしまう。このカットは笑っている、このカットはしゃべっているというような、記号化された細切れの構成で、マンガと同じようにストーリーを絵にしていく。登場人物にどんな動きをさせようか、どんな芝居をさせようかなんて、考える余裕がない。それは少し残念ですね。やはり構図も含め、絵にする意味がないとね。ただ、これはアニメの制作過程の問題もありますが。

『フィルムは生きている』(1958年〜1959年)
天才動画家(アニメーター)の宮本武蔵には、マンガ映画(アニメーション)をつくるという夢がある。5万枚の動画の消失、大切な目の負傷など多くの困難に見舞われ、夢をあきらめかけた武蔵だが、故郷の愛馬アオの幻影に励まされて再びマンガ映画制作を志し、ライバルの佐々木小次郎と対決する。
◾️海外アニメがなぜ受けるのか
海外アニメは細かい芝居がすごいですよね。ポリゴン数の違いなどもあるけど、たとえばミニオンズなんかは、それぞれのキャラクターが驚くほど繊細な芝居をしている。
ミニオンズをつくったイルミネーションは、いまやディズニー、ピクサー、ドリームワークスに並ぶアメリカの4大アニメ制作会社です。イルミネーションはアニメだけでなく、メディアフランチャイズでも成功していますよね。
人材を育てるという意味では、ヨーロッパには職人を育てる専門学校が豊富です。たとえばフランスにはゴブランという非常に優れたアニメーション学校があって、『怪盗グルーの月泥棒』の監督ピエール・コフィンもここの出身です。教える側も最前線で活躍する本物のプロばかりを揃えている。だから学ぶ側も本気で、倍率もものすごく高くて狭き門。こういう場所が、現在の世界のゲームとアニメの供給源になっているんですね。
今の日本との違いは、非常に学びが深いこと。ひとつのことを突き詰めて教えているんですね。だから本当に専門的な能力が磨けるわけです。
◾️人を感動させるのは高度な技術だけじゃない
──日本も負けていられませんし、アニメ表現も進化し続けていますよね。
映像やアニメーションの進化は、「こういうことを表現したい」っていう強いエネルギーを持つ人たちの表出だと思います。だからこそ、CGや3Dがこれだけ発達したわけですよね。たとえば山崎貴監督が『ゴジラ-1.0』でアカデミー賞の視覚効果賞を獲りましたが、あれは彼が特撮やVFXへの熱意を積み重ねた結果ですよね。
──つくり手に熱量があるからこそ、人の心を動かすわけですね。
ただ、人の心を感動させるのは技術だけではないんです。たとえば、『せむしの仔馬』というロシアの古いアニメーションに、火の鳥が出てくる。子供の頃は「こんなにきれいなものは初めて見た」と感動しました。たとえ古いフィルムでも、そういう感動ってあるんです。技術が進化して、ものすごいSFXやCGを駆使した火の鳥を見ても、それが記号化されてしまったら、美しく見えないこともありますよね。
──たしかに、映像のすごさだけではもう感動できなくなっていますね。
今はAI全盛の時代ですが、コンピュータではできないものもたくさんあるはずです。たとえば「そこはかとない色気」みたいなものって、言葉ではうまく表せないでしょう。そういうものをつくっていくのが、人間に残された仕事だと思います。アニメをつくるときに一番大切なのは「キャラクターを生きているもののようにできるかどうか」なのです。
実は言葉で表せないもののほうが多いのです。私たちはChat GPTに対して言葉で命令するわけですから、言葉にできないものは表現もできないものです。
◾️日本アニメ界の強みはストーリーの面白さ
──日本のアニメに勝機はありますか?
日本の強みといえば、やはり物語だと思います。そういう意味で、マンガは強いですよね。究極の話、ペンと紙があればひとりで描けるわけですから、資本がいらない。マンガ家になるには学歴も必要ありませんしね。むしろいろいろな苦労や経験をした人のほうが、世の中を見る目にリアリティがあるから、ストーリーがおもしろかったりもする。物語作家を輩出する素地というのは、幸か不幸か日本はまだまだ衰えていないと思います。
──アニメもストーリーは重要ですよね。
登場人物が2人いたら、物語が生まれる。2人の人間関係をしっかり描かなきゃならないから、やはりストーリーは大事です。
◾️大事なのは「コミュニケーション」の動き
アニメで動かすのは、主に「人」でしょう。人の動きは2つしかなくて、1つは歩いたり走ったり、生活に必要な物理的な動き、もう1つはコミュニケーションのための動きです。つまり、相手に自分の気持ちを伝えたり、あるいは伝わらないように隠したり、すべて何らかのメッセージを表現する動きです。そのコミュニケーションの動きの面白さを、僕らは表現したいわけですよ。それが物語の面白さにもつながっていくわけですから。
──動きに相手への感情を乗せるわけですね。
物語は骨組みですからね。そこに肉づけするのは、やはり芝居です。どうやって線画を人間くさいものにできるかなんですね。昔の映画監督はいい芝居ができるまで、丸1日使ったとか。さすがにテレビアニメの世界では許されませんが。
──アニメは量産されていますからね。特にテレビアニメは時間との戦いでしょうし。
ヒット作をつくってメディアフランチャイズにするというようなシステムをつくらないと、常にアニメーターが疲弊してしまう現状がありますよね。構造を根本的に変えないと、アニメーターは自分のつくりたいものなんてつくれない気がします。
そういう意味では、手塚治虫の名前を後世に残すためにも、ディズニーやイルミネーションのような戦略が必要なのかもしれません。ただ、やはり原作主義のようなものが邪魔しているような気がします。手塚先生のマンガは、どうしてもストーリーが前に出ますから。
◾️ひとつのことを突き詰めるほど、むしろ広がっていく
好きなこと、ひとつのことをずっと突き詰めていくと、いろいろなことがわかってくるんです。自然にわかることもあれば、自分から知りたいと思って学ぶこともある。受動的にも能動的にも積み重なって、広がりが出てくるんですよ。
──なるほど。突き詰めると、広がりが出てくる......。
私自身、マンガのアシスタントからはじまって、アニメーターになって、さまざまな経験を重ねていくうちに大学で教鞭をとるようにもなり、大学では物語論のようなものも教えました。中国の大学で教えるようになってからは、中国史も好きになったり、インドの絵が好きで、ヒンズー教にも興味が出て勉強したり。宗教の世界も、究極に近づくほど言葉では表せないものがありますよね。禅がそうですよ。そういうものを表現してみたくなるわけですよ。
──どんどん広がっていますね。
いくつになっても興味が尽きなくて、あれもこれも知りたくなるんです(笑)。
[第5回に続く]
 山崎潤子
山崎潤子
ライター・エディター。
幼少期より漫画漬けの生活を送ってきた生粋のインドア派。
好きな手塚作品は『ブラック・ジャック』。著書に『10キロやせて永久キープするダイエット』などがある。
バックナンバー
関係者インタビュー 私と手塚治虫 第1回 華麗なる(?)手塚家の生活
関係者インタビュー 私と手塚治虫 第2回 自由奔放な娘と手塚家の教育方針
関係者インタビュー 私と手塚治虫 第3回 母よ、あなたは強かった
関係者インタビュー 私と手塚治虫 小林準治編 第1回 古き良き、虫プロ時代
関係者インタビュー 私と手塚治虫 小林準治編 第2回 昆虫愛がつないだ関係
関係者インタビュー 私と手塚治虫 瀬谷新二編 第1回 冷めることがなかったアニメへの情熱
関係者インタビュー 私と手塚治虫 瀬谷新二編 第2回 いつだって、手塚治虫はみんなの中心にいた
関係者インタビュー 私と手塚治虫 華平編 中国と日本、縁で結ばれた手塚治虫との出会い
関係者インタビュー 私と手塚治虫 池原 しげと編 第1回 『鉄腕アトム』にあこがれて、手塚治虫を目指した少年
関係者インタビュー 私と手塚治虫 池原 しげと編 第2回 アシスタントが見た、手塚治虫の非凡なエピソード
関係者インタビュー 私と手塚治虫 池原 しげと編 第3回 本当にあった、手塚治虫のかわいい!? わがまま
関係者インタビュー 私と手塚治虫 手塚 眞編 第1回 僕がいま、映画『ばるぼら』を撮った理由
関係者インタビュー 私と手塚治虫 手塚 眞編 第2回 手塚治虫が『ばるぼら』で本当に描きたかった心の中
関係者インタビュー 私と手塚治虫 手塚 眞編 第3回 AIでは再現できない、手塚治虫の目に見えない演出のすごさ
関係者インタビュー 私と手塚治虫 濱田高志編 第1回 昭和時代の子供が出会った手塚漫画
関係者インタビュー 私と手塚治虫 濱田高志編 第2回 ひとりのファンと手塚治虫の邂逅
関係者インタビュー 私と手塚治虫 濱田高志編 第3回 手塚治虫がつないでくれたたくさんの縁
関係者インタビュー 私と手塚治虫 濱田高志編 第4回 「手塚作品の復刻版をつくる」意義
関係者インタビュー 私と手塚治虫 伴俊男編 第1回 手塚プロダクションに二度入社した男
関係者インタビュー 私と手塚治虫 伴俊男編 第2回 富士見台時代から大きく変わった高田馬場時代へ
関係者インタビュー 私と手塚治虫 伴俊男編 第3回 アシスタントが見た「手塚治虫」という天才
関係者インタビュー 私と手塚治虫 辻真先編 第1回 89歳の今でも、最新漫画やアニメまでチェック
関係者インタビュー 私と手塚治虫 辻真先編 第2回 日本のテレビ番組、その夜明けを駆け抜ける
関係者インタビュー 私と手塚治虫 辻真先編 第3回 戦争をくぐり抜けてきたからこそ、わかること
関係者インタビュー 私と手塚治虫 辻真先編 第4回 過去から現在まで、博覧強記の漫画愛
関係者インタビュー 私と手塚治虫 辻真先編 第5回 アニメ『ジャングル大帝』の知られざる裏話
関係者インタビュー 私と手塚治虫 萩尾望都編 第1回 漫画家になる決意を固めた『新選組』
関係者インタビュー 私と手塚治虫 萩尾望都編 第2回 漫画家の視点で「手塚漫画」のすごさ
関係者インタビュー 私と手塚治虫 萩尾望都編 第3回 萩尾望都と手塚治虫は何を話したのか
関係者インタビュー 私と手塚治虫 萩尾望都編 第4回 『鉄腕アトム』に見る、手塚治虫の漫画手法
関係者インタビュー 私と手塚治虫 吉村昌輝編 第1回 新人の制作担当からアニメーターへ
関係者インタビュー 私と手塚治虫 吉村昌輝編 第2回 嗚呼、青春の富士見台。虫プロダクションの日々
関係者インタビュー 私と手塚治虫 吉村昌輝編 第3回 手塚治虫との距離が近づいた、高田馬場時代
関係者インタビュー 私と手塚治虫 吉村昌輝編 第4回 手塚治虫という原点があったから、今がある
関係者インタビュー 私と手塚治虫 三浦みつる編 第1回 漫画少年、「漫画家への道」に葛藤する
関係者インタビュー 私と手塚治虫 三浦みつる編 第2回 自ら退路を断って決めた、アシスタント生活
関係者インタビュー 私と手塚治虫 三浦みつる編 第3回 手塚アシスタントのリアルな日々
関係者インタビュー 私と手塚治虫 三浦みつる編 第4回 アシスタントは見た! 『MW手塚治虫』事件と『よれよれの手塚治虫』事件
関係者インタビュー 私と手塚治虫 三浦みつる編 第5回 『The♥かぼちゃワイン』は「あの作品」に影響を受けていた!?
関係者インタビュー 私と手塚治虫 沢 考史編 第1回 新人時代の『チャンピオン』編集部
関係者インタビュー 私と手塚治虫 沢 考史編 第2回 時代によって変化するマンガの世界と価値観
関係者インタビュー 私と手塚治虫 沢 考史編 第3回 天才編集者と天才マンガ家~『ブラック・ジャック』誕生の秘密
関係者インタビュー 私と手塚治虫 石坂 啓編 第1回 「手塚治虫がアイドル」だった少女、夢を叶える
関係者インタビュー 私と手塚治虫 石坂 啓編 第2回 天才の仕事ぶりと「あの都市伝説」の真実
関係者インタビュー 私と手塚治虫 石坂 啓編 第3回 いまだから言える! 「手塚先生、あのときはごめんなさい!」
関係者インタビュー 私と手塚治虫 石坂 啓編 第4回 アシスタントは「手塚番」の編集者よりははるかに楽!
関係者インタビュー 私と手塚治虫 石坂 啓編 第5回 「身近なもの」だったから、私たちは漫画に夢中になった
関係者インタビュー 私と手塚治虫 わたべ 淳編 第1回 僕らは手塚治虫をもっと見上げておくべきだった
関係者インタビュー 私と手塚治虫 わたべ 淳編 第2回 飛び出した名言「あなたたちね、仕事に命かけてください!」
関係者インタビュー 私と手塚治虫 鈴木 まもる編 第1回 あの『火の鳥』を絵本にするというプレッシャー
関係者インタビュー 私と手塚治虫 わたべ 淳編 第3回 超マル秘エピソード「手塚治虫と一緒に〇〇を......!? 」
関係者インタビュー 私と手塚治虫 鈴木 まもる編 第2回 絵本を描いて改めてわかった『火の鳥』のすごさ
関係者インタビュー 私と手塚治虫 わたべ 淳編 第4回 たった16ページで表現できる緻密なストーリー
関係者インタビュー 私と手塚治虫 鈴木 まもる編 第3回 いい絵本には、作者の「好き」がたくさん詰まっている
関係者インタビュー 私と手塚治虫 堀田あきお&かよ編 第1回 『手塚治虫アシスタントの食卓』が生まれた理由
関係者インタビュー 私と手塚治虫 堀田あきお&かよ編 第2回 アシスタント時代を彩った愛すべき登場人物たち
関係者インタビュー 私と手塚治虫 堀田あきお&かよ編 第3回 マンガの神様の超絶技法
関係者インタビュー 私と手塚治虫 堀田あきお&かよ編 第4回 「手塚治虫=時代が生み出した概念」説
関係者インタビュー 私と手塚治虫 野内雅宏編 第1回 新人編集者、マンガの神様の読み切り担当になる
関係者インタビュー 私と手塚治虫 野内雅宏編 第2回 初対面の手塚治虫と、いきなりタクシーで打ち合わせ
関係者インタビュー 私と手塚治虫 月岡貞夫編 第1回 文通から始まった手塚治虫との絆
関係者インタビュー 私と手塚治虫 月岡貞夫編 第2回 手塚治虫の代役で東映に派遣。そしてアニメーターの道へ