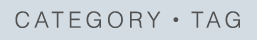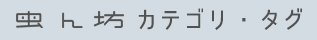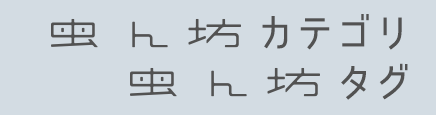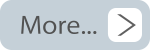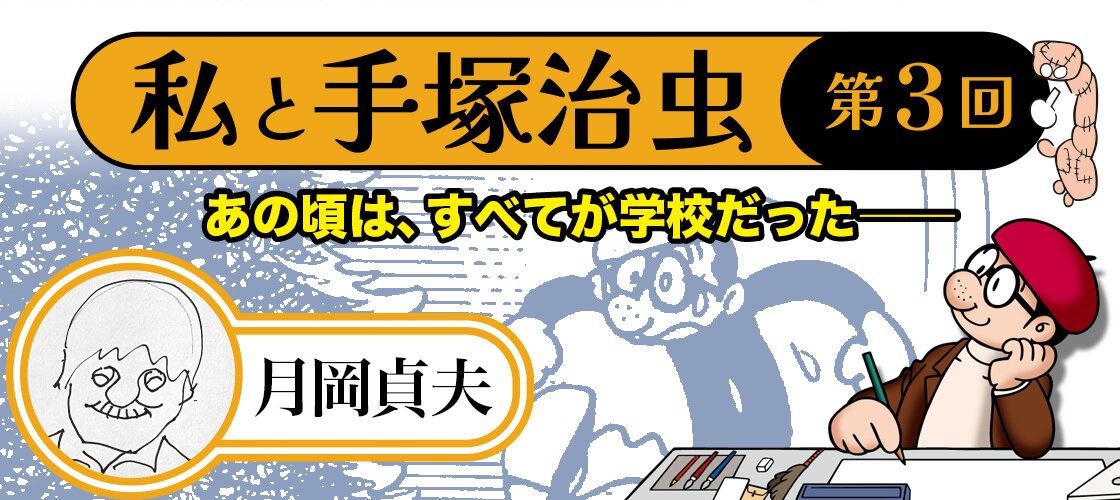
関係者インタビュー
私と手塚治虫 月岡貞夫編
第3回 あの頃は、すべてが学校だった──
文/山崎潤子
関係者に話を聞き、さまざまな角度から手塚治虫の素顔を探っていこうという企画です。今回はアニメーション作家の月岡貞夫さん。「天才アニメーター」と呼ばれた月岡さんは、日本アニメ界のレジェンド的存在です。手塚治虫とのエピソードから、現在のアニメ界の考察まで、さまざまな視点でお話を伺いました。
PROFILE
月岡貞夫(つきおか・さだお)
アニメーション作家。1939年新潟県生まれ。手塚治虫のアシスタントを経て東映動画入社。『西遊記』(1960年)、『ねずみの嫁入り』(1961年)、『わんぱく王子の大蛇退治』(1963年)に携わり、24歳にして東映のテレビアニメシリーズ第1作となる『狼少年ケン』(1963年)の総監督を務める。その後フリーとなり、NHKみんなのうた「北風小僧の寒太郎」(1974年)、CMの富士通のタッチおじさん、明治うがい薬のカバくんなど、多くの作品で知られる。虫プロ作品では『W3』『悟空の大冒険』『リボンの騎士』などに携わる。第45回日本アカデミー賞協会特別賞を受賞。中国美術大学、西安美術大学、北京電影大学客座教授。
◾️一緒に出かけたウォルト・ディズニー展
──手塚先生は、月岡さんのことはずっと一目置いていたのでしょうね。
それはどうだかわかりませんが、アシスタント時代から手塚先生の外出に同行することはよくありました。
よく覚えているのは、1960年に日本橋の三越百貨店で行われた「漫画の歴史と動画芸術 ウォルト・ディズニー展」です。手塚先生が「こういうのがあるんだけど月さんいかない?」と、ぼくだけを誘ってくれました。先生もディズニーが大好きでしたから。
──それは貴重なお誘いですね。
ずいぶん昔の話ですし、あまり知られていないのですが、本当にすばらしい展示でした。原画のパネル展示だけではなく、ショーのような要素があってね。たとえば『白雪姫』で小人が踊るシーン。当時は実写フィルムで踊っている人間を1コマずつトレースして、それをアニメーターが2等身か3頭身のキャラに描き換えるわけです。それをひとつのフィルムにミックスして、見せてくれる。人間の動きとアニメキャラの動きが一緒に映るから「ああ、アニメーションってこうやってつくるんだ」っていうのがわかるようになっているんです。
余談ですが、このとき展示された大量のディズニーアニメのセル画が千葉大学に保管されていたのですが、発見・修復され、2006年に東京都現代美術館でこのときの原画を含む「ディズニー・アート展」が開催されたんです。
◾️大作家同士の会話は「受けているかどうか」
手塚先生が小松左京さんとお会いするときに同行したこともありました。たしか帝国ホテルのラウンジで、「やあやあ、しばらくしばらく」なんて言い合って。
──小説とマンガという違いはあれど、大作家同士ですから、すごい場面ですね。
そこで聞いたのは「手塚くんの〇〇は受けてるねえ」「いやいや、小松さんの〇〇にはかなわないですよ」なんていう会話です。大作家同士がまず交わす言葉が「受けているか受けていないか」なんですよ。
──大作家であっても、まずは「受け」を気にするわけですね。
これは強烈な印象を受けましたね。その後の学生にスピーチをする際の重要なテーマの一つになりました。学生たちは芸術を目指したいというけれど、天下の大作家であっても、常に大衆に受けるかどうかを考えている。それがプロなんですよね。
手塚先生や小松左京さんにはウケるウケない、は作品づくりの根本の問題なのですよ。だからこそ手塚先生も小松さんも作家としては長寿でした。生意気ですが私はウケるということを体系化し学問として捉え、学生に教えてきました。逆に芸術大学などでは芸術としての観点でしかみていないので、なかなか食べてはいけないのですね。
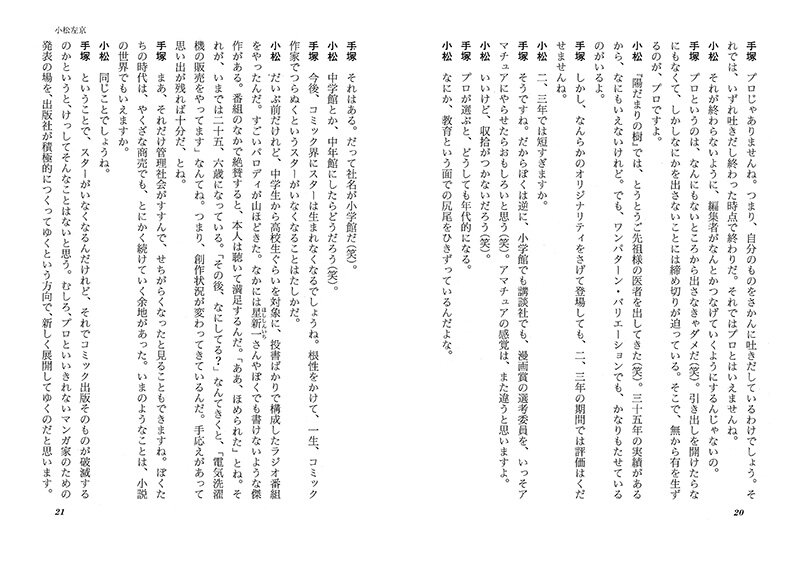
対談相手として小松左京氏が登場。コミック・ブームに端を発し、少女マンガや劇画、子どもの頃読んだマンガ、SF作品など、話題が縦横無尽に広がっていく。対談の中で手塚治虫は「自分のものを吐き出し終わったあと、無から有を生ずるのがプロだ」と語っている。ほかにも種村季弘氏、萩尾望都氏、立川談志氏などとの対談を収録。
◾️トキワ荘で主人公のネーミング論争
話は変わりますが、石ノ森さんと一緒に東映に通っていたとき、よくトキワ荘に寄らせてもらいました。スタジオがある大泉学園までは、新宿から出ているバスで行くわけですが、石ノ森さんはトキワ荘のある椎名町あたりから乗ってくる。バスの帰りに「月さん、寄っていかない?」なんて誘ってくれてね。トキワ荘に行ったり、近くのEDENという喫茶店に行ったりして、みんなでいろいろな話をしました。
その頃、トキワ荘にいた面々の間で盛んに出てきたのも、「何が受けるか」という話題でした。芸術がどうだなんていう話は、いっさい聞いたことがありません。
──やはり、どれだけ大衆に受けるかを気にするわけですね。
本当のプロはみんなそうですよね。藤子不二雄さんの『オバケのQ太郎』ってあるでしょう。主人公の名前は3文字が理想だから、「Q太郎(きゅうたろう)」なんて長すぎると、盛んに議論が交わされていました。つまり、短くてシンプルな名前のほうが人の記憶に残るというわけですよ。
──結果的に「オバQ」と呼ばれて大人気でしたが、主人公のネーミングもそれだけ考えられていたんですね。
あの時代は、すべてが生きた学校でした。手塚先生のところも、東映も、仲間うちで交わす会話からも、本当に大切なことをたくさん教えてもらいました。
◾️「1日600枚」驚異の作画スピード
でも、東映に入社した当時は、手塚先生のところより給料はどーんと落ちたんです。きっと高卒の規約がなかったからでしょうね。でも、しばらくするとさすがに理不尽だということで、上が規約を変えてくれたんです。「月岡は人の10倍仕事をしているのに、大卒の一般社員より給料が低いのはおかしい」って。出来高払いのシステムが取り入れられて、給料がものすごく増えました(笑)。
──そんなに仕事をたくさんしていたんですか?
当時、ディズニーには3分間で1枚の絵を描くアニメーターがいるという話を聞いたんです。じゃあ僕らもやってみようということで、東映の若手アニメーターたち十数人で、1日何枚描けるか競争することになりました。10時から24時まで、休憩を1時間ずつ挟んで......。結果は私が1日600枚、二番手は120枚だったかな?
──えーと......13時間だからで600枚だから......計算すると1.3分に1枚!!!
キャラクターが単体だったからそのくらいは描けたんです。
──月岡さんの作画のスピードは、やはり天性のものなんでしょうか。
自分ではわからないけれど、模写やスケッチをたくさんやっていたからでしょうか。
新潟にいた頃から、とにかく手塚先生のマンガやディズニーの模写ばかりしていたんです。ディズニーファン向けの雑誌のコーナーにディズニーの模写をしょっちゅう投稿して、いつも「新潟県 月岡貞夫」と名前が出ていて、東映に入ってからは「ああ、あの月岡くんかぁ」って何人かに言われたくらい。
◾️安売りしすぎる巨匠
──月岡さんが手塚治虫を分析するとしたら、どんな感じですか。
やっぱり、手塚先生は忙しすぎましたよね。とはいえアイデアマンだから、つくろうと思えば量産できてしまう。作品数を絞っていたら、もっともっといいものができただろうと思います。
でも、時間のかかるアニメーションをテレビの世界に持ち込んだのは、手塚先生の功罪といえるでしょうね。しかも1週間で1本というスタイルを確立してしまった。手塚先生って、大作家でありながらつい安売りしてしまうんですよ。
──マンガの原稿料もあまり上げないようにしていたそうですね。
当時のマネージャーも「手塚は自分のギャラを上げたがらない」と言っていました。上げすぎて仕事がなくならないように、ほどほどのところにしておこうという気持ちがあったようですね。
──あまりお金に固執するタイプでもなかったのでしょうか。
それもあります。でも、手塚先生って決して単純な人ではないんですよ。お金がほしくないわけじゃないけど、それ以上に仕事を続けたいというか、人に求められたいというか。そういう面はつまり、「ウケたい」というところにつながりますね。
◾️1枚上がったら印刷所に走る編集者たち
──頼まれると引き受けてしまう手塚先生の性格もあるでしょうね。
手塚先生はものすごい売れっ子だったから、毎日編集者が7、8人、応接室にぎゅうぎゅう詰めで朝から晩まで原稿待ちをしている。常連の編集者はソファに陣取って、新人の編集者は予備のパイプ椅子を持ち込んでね。
1枚原稿が上がると、たとえば講談社の編集者がそれを持って印刷所に走る。次に1枚上がると、今度は学研の編集者がそれを持って印刷所に走る。そしてまた戻ってきて原稿待ちをする、という状態でした。つまり8人の編集者がいるということは8つの物語を一気に描くのではないということです。ネームを打って貼る写植の作業があるから、時間がないときは1枚でも印刷所に入れたいわけです。
──いろいろなストーリーがあるのに、1枚ずつ切り替えて描くなんて!
私もそうですが、ひとつのことだけやっていると煮詰まっちゃうから、切り替えたほうが新しいアイデアは出てくるんですよ。手塚先生はそういうことも意識的にやっていたのかもしれませんね。
──仕事で気分転換をする感じでしょうか。月岡さんがおっしゃると説得力がありますね。
もちろん、原稿が遅いと編集者同士が険悪になるから、平等に描いてあげようと思っていたのが大きな理由でしょうね。
◾️どんなに忙しくてもテレビは断らない
でも、手塚先生はどんなに忙しくてもテレビ出演の依頼があれば出かけていくんです。
当時の仕事場は2階だったから、編集者に知られないように裏からハシゴを用意させて、2階の窓からこっそり出ていく。編集者がイライラしながら待っているのに、応接室の大きなテレビに手塚先生がニコニコ写っていて、皆びっくりするわけです。この時代のテレビは録画と言うものがないからどうして家から出られたのか??? 出るのを知っていたらどうなっていたかです。
──マンガのシーンみたいな状況ですね。
そうなると編集者たちは「手塚先生、本当に2階にいるの?」なんてマネージャーに詰め寄るわけですよ。そうなるともう嘘はつけないから、マネージャーは平謝りです。
手塚先生としては、気分転換というのもあるだろうけど、基本的には出たがり屋だから(笑)。いつまでも人気者でいたいっていう気持ちも強かったのでしょうね。
[第4回に続く]
 山崎潤子
山崎潤子
ライター・エディター。
幼少期より漫画漬けの生活を送ってきた生粋のインドア派。
好きな手塚作品は『ブラック・ジャック』。著書に『10キロやせて永久キープするダイエット』などがある。
バックナンバー
関係者インタビュー 私と手塚治虫 第1回 華麗なる(?)手塚家の生活
関係者インタビュー 私と手塚治虫 第2回 自由奔放な娘と手塚家の教育方針
関係者インタビュー 私と手塚治虫 第3回 母よ、あなたは強かった
関係者インタビュー 私と手塚治虫 小林準治編 第1回 古き良き、虫プロ時代
関係者インタビュー 私と手塚治虫 小林準治編 第2回 昆虫愛がつないだ関係
関係者インタビュー 私と手塚治虫 瀬谷新二編 第1回 冷めることがなかったアニメへの情熱
関係者インタビュー 私と手塚治虫 瀬谷新二編 第2回 いつだって、手塚治虫はみんなの中心にいた
関係者インタビュー 私と手塚治虫 華平編 中国と日本、縁で結ばれた手塚治虫との出会い
関係者インタビュー 私と手塚治虫 池原 しげと編 第1回 『鉄腕アトム』にあこがれて、手塚治虫を目指した少年
関係者インタビュー 私と手塚治虫 池原 しげと編 第2回 アシスタントが見た、手塚治虫の非凡なエピソード
関係者インタビュー 私と手塚治虫 池原 しげと編 第3回 本当にあった、手塚治虫のかわいい!? わがまま
関係者インタビュー 私と手塚治虫 手塚 眞編 第1回 僕がいま、映画『ばるぼら』を撮った理由
関係者インタビュー 私と手塚治虫 手塚 眞編 第2回 手塚治虫が『ばるぼら』で本当に描きたかった心の中
関係者インタビュー 私と手塚治虫 手塚 眞編 第3回 AIでは再現できない、手塚治虫の目に見えない演出のすごさ
関係者インタビュー 私と手塚治虫 濱田高志編 第1回 昭和時代の子供が出会った手塚漫画
関係者インタビュー 私と手塚治虫 濱田高志編 第2回 ひとりのファンと手塚治虫の邂逅
関係者インタビュー 私と手塚治虫 濱田高志編 第3回 手塚治虫がつないでくれたたくさんの縁
関係者インタビュー 私と手塚治虫 濱田高志編 第4回 「手塚作品の復刻版をつくる」意義
関係者インタビュー 私と手塚治虫 伴俊男編 第1回 手塚プロダクションに二度入社した男
関係者インタビュー 私と手塚治虫 伴俊男編 第2回 富士見台時代から大きく変わった高田馬場時代へ
関係者インタビュー 私と手塚治虫 伴俊男編 第3回 アシスタントが見た「手塚治虫」という天才
関係者インタビュー 私と手塚治虫 辻真先編 第1回 89歳の今でも、最新漫画やアニメまでチェック
関係者インタビュー 私と手塚治虫 辻真先編 第2回 日本のテレビ番組、その夜明けを駆け抜ける
関係者インタビュー 私と手塚治虫 辻真先編 第3回 戦争をくぐり抜けてきたからこそ、わかること
関係者インタビュー 私と手塚治虫 辻真先編 第4回 過去から現在まで、博覧強記の漫画愛
関係者インタビュー 私と手塚治虫 辻真先編 第5回 アニメ『ジャングル大帝』の知られざる裏話
関係者インタビュー 私と手塚治虫 萩尾望都編 第1回 漫画家になる決意を固めた『新選組』
関係者インタビュー 私と手塚治虫 萩尾望都編 第2回 漫画家の視点で「手塚漫画」のすごさ
関係者インタビュー 私と手塚治虫 萩尾望都編 第3回 萩尾望都と手塚治虫は何を話したのか
関係者インタビュー 私と手塚治虫 萩尾望都編 第4回 『鉄腕アトム』に見る、手塚治虫の漫画手法
関係者インタビュー 私と手塚治虫 吉村昌輝編 第1回 新人の制作担当からアニメーターへ
関係者インタビュー 私と手塚治虫 吉村昌輝編 第2回 嗚呼、青春の富士見台。虫プロダクションの日々
関係者インタビュー 私と手塚治虫 吉村昌輝編 第3回 手塚治虫との距離が近づいた、高田馬場時代
関係者インタビュー 私と手塚治虫 吉村昌輝編 第4回 手塚治虫という原点があったから、今がある
関係者インタビュー 私と手塚治虫 三浦みつる編 第1回 漫画少年、「漫画家への道」に葛藤する
関係者インタビュー 私と手塚治虫 三浦みつる編 第2回 自ら退路を断って決めた、アシスタント生活
関係者インタビュー 私と手塚治虫 三浦みつる編 第3回 手塚アシスタントのリアルな日々
関係者インタビュー 私と手塚治虫 三浦みつる編 第4回 アシスタントは見た! 『MW手塚治虫』事件と『よれよれの手塚治虫』事件
関係者インタビュー 私と手塚治虫 三浦みつる編 第5回 『The♥かぼちゃワイン』は「あの作品」に影響を受けていた!?
関係者インタビュー 私と手塚治虫 沢 考史編 第1回 新人時代の『チャンピオン』編集部
関係者インタビュー 私と手塚治虫 沢 考史編 第2回 時代によって変化するマンガの世界と価値観
関係者インタビュー 私と手塚治虫 沢 考史編 第3回 天才編集者と天才マンガ家~『ブラック・ジャック』誕生の秘密
関係者インタビュー 私と手塚治虫 石坂 啓編 第1回 「手塚治虫がアイドル」だった少女、夢を叶える
関係者インタビュー 私と手塚治虫 石坂 啓編 第2回 天才の仕事ぶりと「あの都市伝説」の真実
関係者インタビュー 私と手塚治虫 石坂 啓編 第3回 いまだから言える! 「手塚先生、あのときはごめんなさい!」
関係者インタビュー 私と手塚治虫 石坂 啓編 第4回 アシスタントは「手塚番」の編集者よりははるかに楽!
関係者インタビュー 私と手塚治虫 石坂 啓編 第5回 「身近なもの」だったから、私たちは漫画に夢中になった
関係者インタビュー 私と手塚治虫 わたべ 淳編 第1回 僕らは手塚治虫をもっと見上げておくべきだった
関係者インタビュー 私と手塚治虫 わたべ 淳編 第2回 飛び出した名言「あなたたちね、仕事に命かけてください!」
関係者インタビュー 私と手塚治虫 鈴木 まもる編 第1回 あの『火の鳥』を絵本にするというプレッシャー
関係者インタビュー 私と手塚治虫 わたべ 淳編 第3回 超マル秘エピソード「手塚治虫と一緒に〇〇を......!? 」
関係者インタビュー 私と手塚治虫 鈴木 まもる編 第2回 絵本を描いて改めてわかった『火の鳥』のすごさ
関係者インタビュー 私と手塚治虫 わたべ 淳編 第4回 たった16ページで表現できる緻密なストーリー
関係者インタビュー 私と手塚治虫 鈴木 まもる編 第3回 いい絵本には、作者の「好き」がたくさん詰まっている
関係者インタビュー 私と手塚治虫 堀田あきお&かよ編 第1回 『手塚治虫アシスタントの食卓』が生まれた理由
関係者インタビュー 私と手塚治虫 堀田あきお&かよ編 第2回 アシスタント時代を彩った愛すべき登場人物たち
関係者インタビュー 私と手塚治虫 堀田あきお&かよ編 第3回 マンガの神様の超絶技法
関係者インタビュー 私と手塚治虫 堀田あきお&かよ編 第4回 「手塚治虫=時代が生み出した概念」説
関係者インタビュー 私と手塚治虫 野内雅宏編 第1回 新人編集者、マンガの神様の読み切り担当になる
関係者インタビュー 私と手塚治虫 野内雅宏編 第2回 初対面の手塚治虫と、いきなりタクシーで打ち合わせ
関係者インタビュー 私と手塚治虫 月岡貞夫編 第1回 文通から始まった手塚治虫との絆