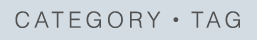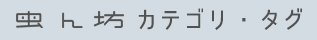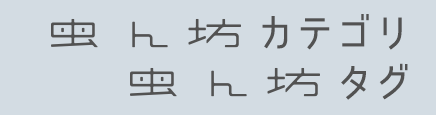スペシャルインタビュー第6回のゲストは、世界で活躍する美術家、横尾忠則さん。長きにわたり美術家・グラフィックデザイナーとして活躍を続ける横尾さんですが、その日常生活とはどのようなものなのでしょうか。後編では、貴重なUFO体験のお話や、普段の過ごし方、制作へのモチベーションなどについてお聞きしました。
◆前回の記事:スペシャルインタビュー第6回 横尾忠則さん【前編】
横尾忠則 Tadanori Yokoo
1936年兵庫県生まれ。美術家。72年にニューヨーク近代美術館で個展。その後もパリ、ヴェネツィア、サンパウロ、バングラデッシュなど各国のビエンナーレに出品し世界的に活躍する。アムステルダムのステデリック美術館、パリのカルティエ財団現代美術館での個展など海外での発表が多く国際的に高い評価を得ている。2012年、神戸に横尾忠則現代美術館開館。2013年、香川県豊島に豊島横尾館開館。2015年、第27回高松宮殿下記念世界文化賞受賞。作品は、国内外多数の主要美術館に収蔵されており、今後も世界各国の美術館での個展が予定されている。
https://twitter.com/tadanoriyokoo
―――ものすごく頻繁にUFOを見るようになったとのことですが、なにかきっかけがあったんでしょうか。
横尾忠則さん(以降、横尾) 子供のころからそういう不思議な体験は度々あったんですよ。たとえば、流れ星が流れている間に願い事をすると成就するって言われていますよね。欲しいおもちゃがある時とかに願い事をしたいと思って下駄を履いて外に出ると、いつも流れ星がやって来るの。だから、流れ星は偶然見るものではなくて、願望がある時にみるようになったんです。
―――横尾さん、やはり、何かもっているのでは......? 幼い頃からそういったパワーがあったんですね。
横尾 高校時代に建物の少し上にUFOがいたのが最初で、頻繁にUFOに遭遇するようになったのは大人になってからです。インドのピンク・シティのホテルの庭で涼みながら星空を見ていたら、ちいさな光が塊になってブワーっとこっちに向かって来たんです。インドの飛行機はすごいなぁって思ってたら僕の頭上にきたところで光がバラバラに弾けて、一瞬でなくなったの!
―――ええ~!
横尾 その当時はUFOを見たいって思って空を見上げると、15分くらいで来てくれた。どこでも見たいところで見れちゃうようになった。
―――すごすぎます。見れるというか、呼んでいるというか......!
横尾 あまりにも頻繁にUFOを見るもんだから、もう興味を持たざるを得なくなって、今まで全く興味のなかった宇宙やUFOの世界にハマってしまいました。"ハマらされた"と言ったほうがいいかな。夜、眠ると必ず夢にUFOや宇宙人が出てきて夢の中でUFOに乗っけられて、ほかの惑星に行ったり北極やチベットの奥にも連れて行かれたりしました。
家族に今日もUFOに乗りに行くよ、なんて言いながら寝たりね(笑)。
―――UFO、ぜひ見てみたいんですけど、今も呼べるんですか?
横尾 今はUFOのことを考えなくなったから、最近は見てないですね。でも、今でも来いと思えば現れるかもしれないけど。そんなわけで、UFOとの遭遇をきっかけに宇宙に興味をもってしまって、モチーフとして好んで描いていた時期がありました。

―――UFOまで呼べてしまう横尾さんですが、普段はどのような生活をしているのか大変興味があります。一日の過ごし方を教えてください。
横尾 その日によって違いますけれど、10時前には起きて、今日みたいな取材を受けたり、依頼の打ち合わせをしますね。午後は制作するときもあるし、アイディアが浮かばなかったらなにもしないってこともあります。今日は描きたくないって時もある。そういったときは、エッセイを書いたり、本を読んだり、そんな感じですね。変わり映えないんです。
展覧会が近づくと、毎日制作しますよ。そのためにワーッと描いて、送ってしまうと一段落。で、しばらくは何もしないでボヤーっとしてる。
―――忙しい時と、そうでないときの差が激しそうですね。
横尾 そうですねぇ。集中するときとそうでないときの違いがありますね。続けて描いたとしても5、6時間かな。昔は徹夜もしてましたけど、今はそんなのできないですよ。手塚さんみたいに毎晩徹夜はできない(笑)。
―――たとえば制作に行き詰ったときに、気分転換にはなにをしますか?
横尾 一番気分転換になるのは絵を描くことなんです。絵を描いて疲れて、その疲れを取るためにまた絵を描く。絵が僕の主治医みたいなものですね。思えば、体調が悪くて病院に行っている間は、絵から離れている期間なんですよね。だから、絵が養生訓みたいなところがありますね。
でも僕は、同じスタイルの絵を長期にわたって描くというのが苦手なんです。性格的なものでね、飽きっぽいんですよ。だから、ひとつのことをやっていてもすぐに飽きちゃう。毎日違う絵を描くのは平気なんですよ。むしろそのほうが僕にとっては自然なこと。とにかくテーマも技法もぜんぶ変えて描かないとダメなんです。
―――近年は展覧会のための制作はもちろん、Duran Duranのアートワークを手掛けるなどさまざまな活動を経て、どのように作品の"スタイル"が変化していきましたか?

横尾 「最近」のスタイルはありませんが、「今日」のスタイルならあります。明日はまたガラッとかわるでしょうね。ここにある絵もそうだけど、あれを描いてこれを描いて、リアルな絵も描くし、装飾的な絵も描くし、これらを全部同じ時期に描いてしまうわけです。
このたくさん耳が集まっている絵は、最近難聴になってきたから、それをテーマに描いたもので、半抽象画ですね。

―――それぞれ、絵の色彩も全然違いますね。
横尾 僕はスタイルがないから、ある意味なんでもアリってことになっちゃうんですよねぇ。だから、その時思ったこと、描きたいもの、依頼で描くべきものも含めてその時の気分で表現を変えながら描きます。
―――今後、描いてみたいモチーフはありますか?
横尾 描きたいものも、その日になってみないとわからない。でも、今までの長いキャリアの中で描いてきたモチーフを、また描き直してみようかと漠然と思っていますね。過去の作品の反復は、僕のスタイルです。
―――アトリエには、そこかしこに猫の絵が置いてありますが、これも今描いている作品なのでしょうか。


横尾 ああ、これは死んでしまったうちの猫です。死んだ猫をレクイエムするということで、できれば100匹描こうと思って。今は、60匹くらいかな。全部同じ子ですよ。
これはあまりデフォルメしないで、写実的に描いてます。これは、僕と猫との距離感の問題で、愛があるゆえにこの猫を突き放して抽象的に描くことはできません。生きていた頃を回想しながら描くわけですから。だから100点の猫に関しては、この一貫したスタイルで描いていこうと思っています。
もしかしたらと思うけれど、手塚さんが僕の展覧会に見に来てくださったのは、そういう僕の変則的なスタイルに興味を持たれたのかもしれないね。手塚さんの場合、アトムはどんなにスタイルを変えて描いたとしても、それはアトム以外の何者にもならないわけですから。漫画という決まったスタイルに従って描く、そういう仕事の仕方をしていらっしゃった。僕はまるで正反対のことをやっていたから、そこが面白かったのかもしれないね。

―――来て驚いたのですが、壁にはアトムの描かれている作品がありますね!
横尾 あれはスイスで展覧会をやったときのポスターで、僕の展覧会と日本の漫画の展覧会の2本立てだったんですよ。その時は手塚さんの絵もたくさん出ていたので、以前手塚プロから頼まれてアトムを描いた絵から引用したものです。たまたまポスター貼っておいて良かったな(笑)。
―――横尾さんには、マンガ家・手塚治虫はどのように映りますか?
横尾 漫画を描かなきゃいけない、それが手塚さんの運命だったと思うんですよね。はやくに亡くなられてしまったけど、その限られた時間の中でやることを成し遂げた。僕にはがむしゃらに描いて、がむしゃらに生きておられるように見えて、もっと他に好きなことをすればよかったのにと思いますけれど、きっと手塚さんにとっては漫画を描くことが一番好きなことだったんでしょうね。
―――もし、今また手塚治虫に会えるとしたら、どんなことをしたいと思いますか。
横尾 手塚さんは、もう別の世界におられるわけで、僕もこの先そこへ行くはずだから、そこで会いたいですね。会っても、何をしようということにならないと思うけどね。お互いにやりたいことをやってしまったわけだから。
―――お互い、絵を描くわけでもなく?
横尾 「手塚さん、忙しかったですねえ」「横尾さんもね」って言い合うのかな。これからは、せっかくゆっくりできるんだから、遊びましょうよって。
人間の死というのは、今生きている世界からちょっと違った道にスッとずれる感覚だと思うんです。だから、そういう意味ではそんなにこの世界と変わらないんじゃないかとも思う。『火の鳥』でも『ブッダ』でも描かれていると思いますけれど、こちらでの生き方が、死んでからの世界に反映するわけだから、できるだけ向こうでは楽しんで生きて行きたいですよね。
漫画って、まさに現世を楽しむためのメディアだと思います。ファンタジーの世界を描いて人々を楽しませる、そういう意味ではバイブルかもしれない。バイブルを生み出した手塚さんだからこそ、今でも手塚さんの作品が読み継がれているんでしょうね。


なんと、横尾さんがアトムを描いてくださいました! アトムの集合体は、横尾さんのコラージュ作品を髣髴とさせる出来。
横尾さん、お忙しい中、貴重なお話をありがとうございました!
●バックナンバー
生誕90周年企画 スペシャルインタビュー