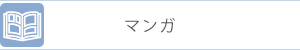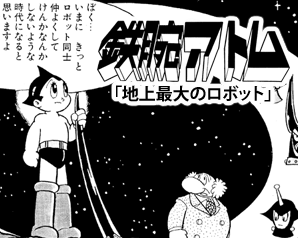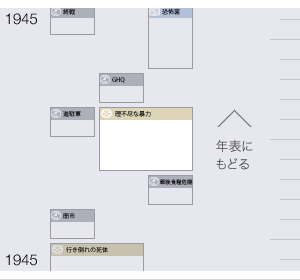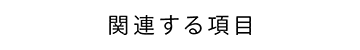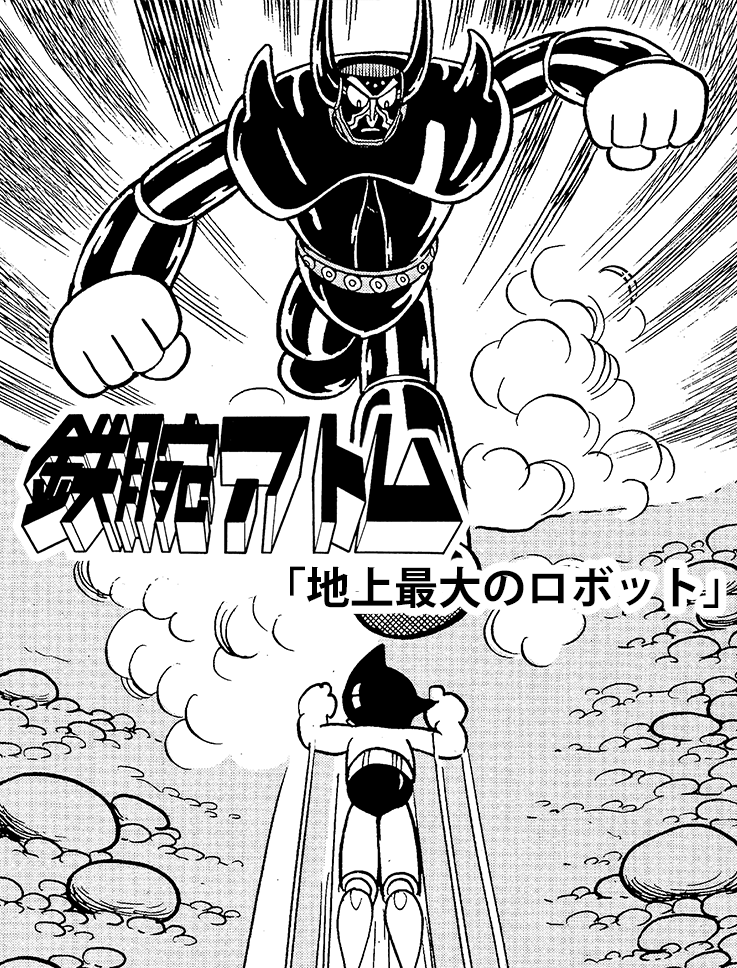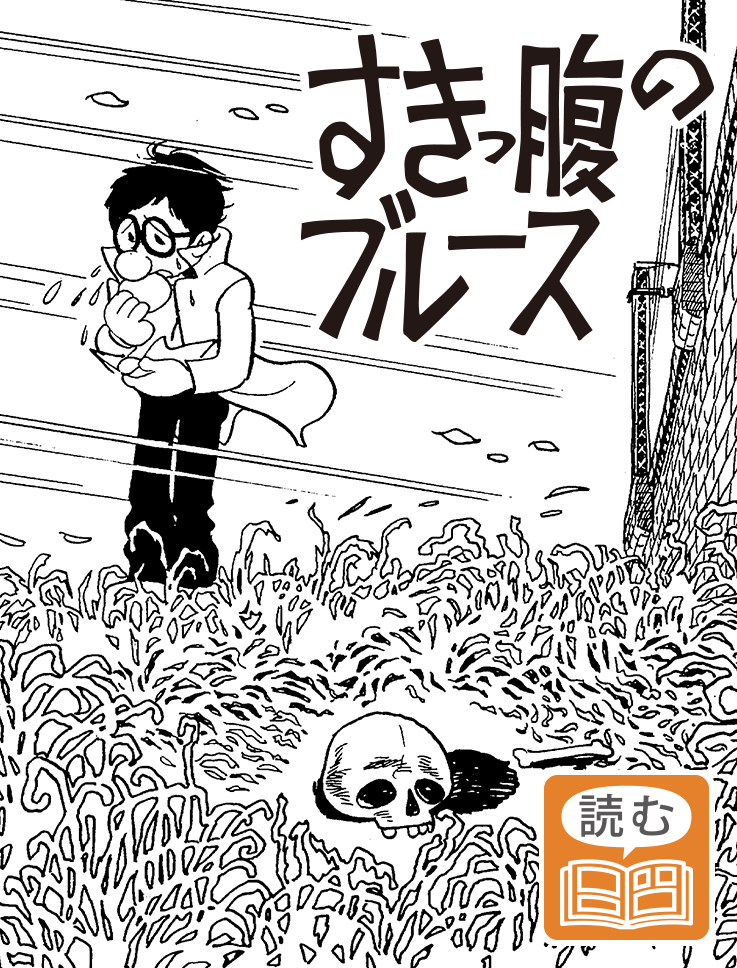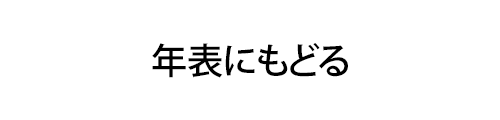理不尽な暴力
1945年頃【16才】
占領軍の兵士に理不尽な暴力を受けた手塚治虫は、意思の疎通の欠如を呪います。この経験が異なる存在同士の軋轢という作品のテーマにつながっていきます。
手塚治虫エッセイ集より
そして、占領軍がやってきた。
「ヤンキーが来たらなぐり殺されるぞ」
「なにもかも強奪されるぞ」
「女子供は外へ出るな!」
という噂(うわさ)をよそに、かれらはやってきた。
ジープに乗り、軍服をスマートに着こなし、すこぶるかっこよく(この時代には、こんなことばはなかった……)かれらはやってきた。
都会へ、農村へ、集会場へ、ビルの中へ、そして、学校へ……。
現金なもので、相手がさほど危険なものでなく、一応紳士であるとわかると、大衆はやたらにべたべたしだした。
マッカーサーの占領政策の中の軍規律はかなり厳しいものであったらしい。
表面的にはにこやかで、博愛精神の押しつけを始めた。それが同情と慰撫(いぶ)に飢えている大衆の目には、天から降った英雄のように見えた。
女性にはやたらと慇懃(いんぎん)だが、かとおもうと、しきりに暴力沙汰(ざた)を繰り返し、そして、たいてい日本人側は泣き寝入りするよりしかたがないのであった。
宝塚もご多分にもれず米軍高級将校の宿舎になった。
ある日、四、五人の酔っ払い兵がぼくとすれちがった。
「××××××」
と、兵隊がぼくに何か訊(たず)ねた。
残念ながら、「敵性語」ということで英語の勉強を中断されたっきりのぼくにとっては、まったくチンプンカンプンである。
「ホワット? ホワット!」
と訊(き)き返すのがせいいっぱいだ。
するとたちまち、ボカーッとなぐられて、ぼくは地面へ叩きつけられた。
痛さに耐えかねて起き上がれない。
ウワッハハハ……笑いとばして米兵は行ってしまった。
手も足も出ない。
占領軍に反抗すれば、射殺されても文句が言えない時代なのである。
腹立たしいやら口惜しいやら、意思の疎通の欠如を、ぼくはひどく呪(のろ)った。
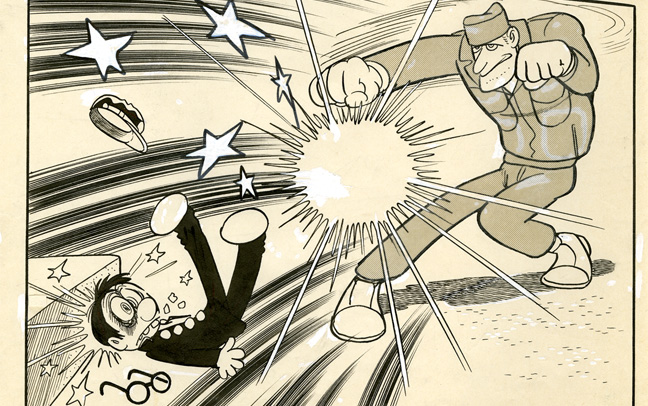
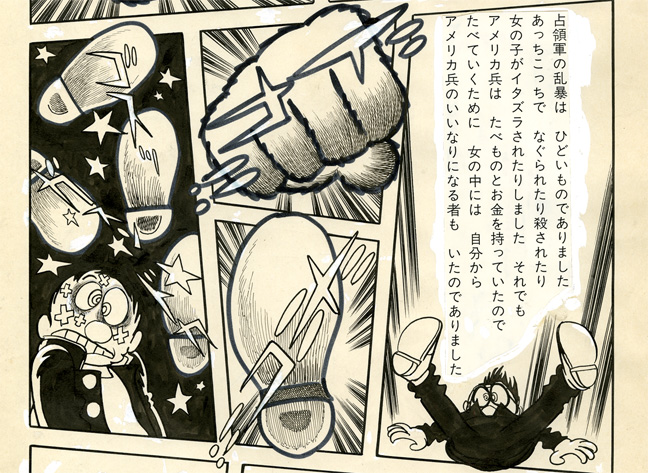
マンガ「すきっ腹のブルース」原画より
当分のあいだ、この厭(いや)な思い出はぼくから頑強に離れず、しぜん、ぼくの漫画のテーマに、そのパロディーがやたらと現れた。
地球人と宇宙人の軋轢(あつれき)、異民族間のトラブル、人間と動物との誤解、そして、ロボットと人間との悲劇……アトムのテーマがこれなのである。
講談社版手塚治虫漫画全集『手塚治虫エッセイ集 1』より
(初出:1969年毎日新聞社刊『ぼくはマンガ家』)