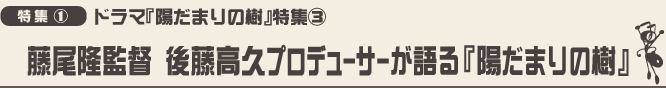
4月6日から始まったNHK BS時代劇『陽だまりの樹』もいよいよ佳境となりましたね! 毎週の放送で万二郎と良庵の運命にドキドキしたり、思わず笑っちゃったり、ホロリとしたりされていることと思います。
今月の虫ん坊では、藤尾隆監督と、後藤高久プロデューサーに、時代劇『陽だまりの樹』の制作秘話を伺いました!
関連情報
『陽だまりの樹』ドラマ化決定!NHKBS時代劇にて今春放送開始
NHKBS時代劇『陽だまりの樹』オフィシャルサイト
陽だまりの樹 NHKドラマスタッフブログ
●『陽だまりの樹』の魅力
——手塚治虫のマンガとしての『陽だまりの樹』の魅力はどこにあるとお考えですか? また、今この時代に『陽だまりの樹』をドラマ化する狙いはなんですか?
後藤プロデューサー(以下、後藤):
このドラマは、「幕末」ということが一つのキーワードですが、明確な時代の転換期であり、混乱期でもあった幕末に、現代の日本人はとても親近感を持っているのではないか、と思います。長年続いた政権が交代して政治が混乱し、経済的な外圧にさらされ、大きな天災に見舞われている状況なんかを見ると、現代と幕末が妙にリンクしているように感じられて、とりわけ親しみを覚えるのではないでしょうか。
手塚治虫先生は権力側ではなく、市政の人々の目から時代を描いていて、そこがユニークであり、多くの視聴者の方々の共感を呼ぶはずです。また、物語もギリシャ悲劇的なセッティングで、運命に抗ってでも生き、最後には滅んでいくヒーローという筋立てには、大きなカタルシスがある、と感じます。観ればある種の勇気がわいてくる。非常に日本人の心の琴線に触れる作品だ、と考えています。
藤尾監督(以下藤尾):
幕末の「勤皇の志士」という言葉があるじゃないですか。あの言葉に象徴されるイメージとしては、あの頃の人たちはみな志が高くて、皆が皆、「こうと決めたらこうだ!」というようにやり遂げていた、というように思いがちなのですが、手塚治虫先生が描いた幕末はそうではなくて。今と同じく、無名の人たちは自分がどうあるべきなのか今ひとつ分かっていなくて、いろいろな人に影響を受けながら、自分の道を見つけていきますよね。この市井の人々の姿が、今の世の中の「無党派層」の多さにリンクするところがあって。現場で、成宮(寛貴)くんともよく「昔も今も、変わらないんですね」というようなことを話していたんです。時代は違えど、人の生き方は変わらない、良い意味で「歴史は繰り返す」というような視点に親近感を感じています。
決して、「昔はこうだった」というような、現代と過去を区別する視点で捉えない、というポリシーですよね。
また、僕の勝手なイメージかも知れませんが、手塚先生の原作には、変に斜に構えるでもなく、敷居を高くするでもない、いかに「人間くささ」を伝えるか、というところがあるように思います。
従来、時代劇というと、ものすごく長い間があって、尺八の音色がして(笑)というようなものを想像するのですが、手塚治虫先生のムードは必ずしもそうではない。今に通じる親近感がほしいですし、原作のユーモア、それに夢や希望というようなものが画面から出てくるようでないと、見る方を裏切るものになるかな、と。
後藤:
金曜時代劇というのは、もともと大河ドラマとは違った時代劇をやる、という番組枠ですから、ストーリーをどう楽しむか、という方向に重きを置いています。今回の『陽だまりの樹』も、時代劇を作るぞ!というよりは、人間ドラマをどう描いていくか、ということに主眼を置いています。
いっぽうの大河ドラマでは、歴史ドラマという位置づけもありますので、それとは少し違ったテイストで観てもらえるように考えています。
——近年、時代劇そのものがあまり作られなくなりつつありますが、NHKのなかで、時代劇や大河ドラマに対する創り方が変わった、というところはありますか?
後藤:
われわれ局側が変わった、というよりは、視聴者の皆さんの時代劇や、大河ドラマの見方が変わった、と感じるところはあります。昔は、夜8時のNHK大河ドラマ、というと、家族そろってお茶の間で見るスタイルでしたが、今は、一人で見ている方も多いですし、歴史好きの方だから見るというふうに変わってきましたね。
また、若い方や、とりわけ女性を意識するようにはなりました。今は、テレビドラマを見る方は女性のほうが多いですから。とはいえ、その視聴傾向がずっと続くわけでもないので、いろいろなバリエーションを持って作っていくことは大切です。そういったところでは、今も昔も変わらないと思っています。
●キャスティング・人物設定
——藤尾監督から見た、主役の二人の魅力ですが。
藤尾:
記者会見でも申し上げましたが、市原隼人さんは、いわば宝石の原石に近い感覚を持っているんですよ。色がついていなくて、まっさらなんですね。演出する側からすると、腕試しをされているような気持ちになります。変な色を付けられない、というか。
市原さんと万二郎には、確かに共通点が多いと思います。ですが、カットがかかると、彼は人が変わった様な顔をするんですよ。「カット」というと、解き放たれたような表情をして、たまに、その顔がほしいときがあるんですよね。でも、彼の中では、それは芝居ではないので(笑)。出来るだけそれが本番中に出るように、合間でバカ話をしにいったりするんですけれども。
成宮寛貴さんも、本質は万二郎なんです。決して、良庵ではないんですよね。良庵っぽく見えますけど。とても真面目なんです。僕から見ると、どことなく二人は似たもの同士なんですよね。
真面目で、直球で来る。直球の質はすこし違うんですが。成宮さんは、切れのある直球タイプ、市原さんは、小手先の工夫を省みない、剛速球タイプですね。
——脇を固める俳優さんたちも、魅力的な方ぞろいですが。
藤尾:主役の二人、万二郎と良庵、というのは、時代劇としてはちょっと変化球にみえるかも知れません。当時の割には、軽快なやり取りがあったりして、ギャグをやるわけではないのですが、結果的に笑わせるような芝居になったり。そうすると、本線から外れる部分もあるんですよね。
彼らに、自由に芝居をしてもらうためには、周りをしっかり固めておく必要があります。これは、今回に限らず、ドラマ作りの決まりごとのようなことなのかも知れません。
女性ではヒロインのおせき、それから、良庵、万二郎のお母さんたちは、ねじまげる必要がないんですよ。おせきさんは、日本古来のつつましさをもった女性ですよね。万二郎の母・おとねは武家に生きる女性ですから、厳粛な面をもった、厳しい優しさを持っていますし、良庵の母であるおなかは町医者のご新造さんですから、懐の深い、ちょっとしたことには目をつぶる器量をもった、からっとした肝っ玉母さん、という位置づけで、とてもいい支えになっていると思います。
——成宮さんも、家族の団欒を演じるのが難しくもあり、楽しかった、とおっしゃっていました。
藤尾:第1話でいうと、伊武谷家よりも手塚家のほうをより長く描いています。前半の話が奥医師の話に傾いていたせいもあるんですけれども、実は、武家の厳しさ、というのは、何シーンも重ねるとちょっと、おなかいっぱいになるところがあるんですよね。手塚家を描くときは、親しみやすい、ホームドラマに近い日常の楽しさがだせるんです。
今はどんどん晩婚が進んでいますが、ああいう団欒というのはやはりいいものですよ。若いときはそういうものがなくても暮らしていけますが、年をかさねていくと、とてもかけがえのないものだな、と思います。昔なら当たり前にあったああいう団欒も、いまや希少価値になりつつありますよね。
——奥医師の多紀誠斎はいかにもどっしりとしていました。
藤尾:
前半のシリアスなクライマックスとして、奥医師と蘭方医たちの確執がかなりの部分を占めます。種痘所を設立しようとする手塚良仙・良庵らの前に立ちはだかる権力、という構図ですよね。奥医師たちは言ってみればヒール的なポジションで、親玉の多紀誠斎を目黒祐樹さんにお願いしたのですが、その目黒さんと現場で話したのですが、やはり、自分が苦労して立ち上げたものを守るのは当然だ、と。やはりそれなりの努力があって、いまの地位がある。ところが時代の流れとともに蘭学が入り込んできて、自分の牙城が脅かされることになる。それをなんとか押しやろうとするのは、当然ですよね、と。それをしっかり意識することで、またそこにも人間くささがでるんじゃないかな、と言っていました。
多紀誠斎を初めとした奥医師たちには、ヒールのポジションながら、どこか同情しながら演出をしています。
——『陽だまりの樹』は虚実がからまった作品ですが、実在の人物についてはどのように描かれるのでしょうか?
藤尾:福澤諭吉についてはすでにキャスティングが決まっていて、崎本大海さんにお願いしています。今週も西郷さんが登場したりしますが、あまり、歴史上こういうひとだった、というのは意識しないようにしています。彼らもまた、成し遂げる前の段階にあるわけですから。若き日の彼ら自身もまた、自分がどういう人物で、どんな器なのか、分かっていないほうが新鮮だと思うんですよ。福澤諭吉のセリフにも、「お前、塾なんか開いたらどうだ」「まあ、そのうちな」というような、軽いやり取りを入れましたが、まあ、そのようににおわせる程度で、もちろん、志はあるんですが、まさか自分が、21世紀の御札の顔になるだなんて、そんなことまでは思っていないわけで(笑)。ですから、「偉人」を演じるという意識が過重にならないように、あくまで、手を伸ばしたら届くところに居る人物、というのが、有名無名問わず、『陽だまりの樹』の登場人物みんなに共通しているところだと思います。
とはいえ、「手を伸ばせば届く」というのは、あくまで市井の側にいる万二郎が懸命に生きているからなんですよね。誰しもが届くというわけではなくて。そこが一番、この作品のキーになるところなんですけれども。
●シリアスな事件に切り込む
——震災後、「安政の大地震」を描くことについて、物議や躊躇はあったのでしょうか?
後藤: ことさらに恐ろしさを強調するような、あるいは娯楽的に描く、ということは決してしてはならない、と誰しもが思っていました。しかしながら、日本はそれこそ千年以上昔から、大地震がたびたび起こっていたことは事実ですから、それをことさらに覆い隠すこともない。ですから、安政の震災については、そのような天災に遭遇した際に、万二郎というキャラクターがどう行動したのか? 良庵はどう思ったのか? ということをきちんと描くことができれば、それはぜひとも描くべきシーンだ、と考えました。
確かに、被災地の方の中には、地震の描写に過敏になっていらっしゃる方もいらっしゃると思いますので、強調したような描写は控えましたが、とりわけ万二郎にとってその後の運命を決める必要不可欠な事件ですからね。
藤尾:そうですね……。
一話のラストの前、二人が藤田東湖先生の話を伺った後、橋の上で話すシーンですね。僕自身撮りながら、ああやって腹を割って話せる友達が、果たしていたのだろうか? と改めて考えましたね。現場で、モニターで見ながら、まずそこが羨ましくてね。将来を嘘偽りなく言い合えるような友人がいる、というだけでもとても幸せで、しかも相手の良いところも悪いところも知っていて、その上で尊重しあえる絆を感じさせる、という。お気に入りのシーンです。
あのシーンが上手くいったので、あの続編を、最終話に提案させていただきました。同じ場所で一芝居撮ろうか、と。
——藤尾監督が撮られた回のなかで、一番お気に入りはどのシーンですか?
藤尾:地震が描かれる第3話は、残念ながら僕の演出担当回ではなかったのですが、いわば一番、万二郎というキャラクターが出やすい場面ですよね。
「静」と「動」のメリハリが一番の万二郎の見せ場であって、普段は、とても静かで、言ってみれば「静」の美しい男です。でも、何か事件が起こると、人が変わったように動き出す。現代も然りですが、周りの人やいろいろなものを気にしてしまって、動きたくても動けない人間が多い中で、ためらいなく行動できるというのは一つの魅力です。もし僕が撮るのなら、そのあたりには相当凝って撮ったと思います。
●原作をいかに脚色するか?
——ところで、あの原作を12話という枠にまとめるのは大変だったのではないでしょうか。
後藤:原作の長さからすれば、それこそ大河ドラマにもなりそうなボリュームですから、たしかに大変でした。
なるべく特定の人物や事件にフォーカスをしていき、筋を整理していきました。たとえば、お品さんのエピソードなんかは薄くしていきながら、万二郎にはフォーカスをあてていく、というような方法ですね。
できれば続編なんかもやりたいところではあるのですが、今回で最後まで描いてしまいますので、続編があるとしたら、ひとつ中盤ぐらいに戻って…(笑)。そこは惜しいところではあるんですけれども。
僕らの企画としてのドラマ『陽だまりの樹』では、やれるところは全てやって、物語の実の部分はちゃんとお見せできる形にしようと思っています。
ただし、原作マンガを読んでいる方には、それぞれに思い入れのあるシーンがあるかと思いますので、中には、「俺の好きなあのシーンがない!」というようなこともあるかもしれません。そこは時代劇『陽だまりの樹』として見ていただいて、逆に、「そうきたか」というところを楽しんでいただきたいです。
——NHKBS時代劇の枠は、ご家族で楽しむ方も多い枠だと思いますが、原作にあるエロティックなシーンや、切り合いなどの恐ろしいシーンはやはり、表現に気をつけましたか?
後藤: それは確かに気をつけました。テレビとして、見せてはいけないものは上手く見せないようにしながらも、人物の性格や、ドラマの内容は損なわないようにしています。
藤尾:一話の冒頭で、女郎屋のシーンがあるじゃないですか。ああいうのも、やろうと思えばいくらでもいやらしくなってしまいますが、やはり良庵のキャラクターであるとか、コミカルな演技であるとかを加えることで、必要以上にいやらしくないようにすることは出来るんですよね。
実はあのシーン、現場ではもう1カット撮っているんですよ。二人が倒れた後に、足を映したカットを撮ってあって、編集でつないでいたんですが、「いらないな」と思って。全体のすがすがしさの中ではかえって邪魔かな、と思って、はずしました。
●それぞれの「手塚作品」
——後藤プロデューサーの御好きな手塚作品はなんですか?
後藤:僕は、「三つ目がとおる」が好きですね。ミステリアスな古代史なんかの雰囲気がたまりませんね。今の撮影技術であれば、あの作品のファンタジックな部分も上手く撮れると思いますし、ぜひ自分が映像化に携わりたい作品です。
——藤尾監督にとっての手塚作品についてお伺いしたいのですが、いつごろ初めて読まれましたか?
藤尾:出会ったのは割合に遅くて、この仕事を始めてすぐに、初めて読んでみました。実は僕は、政治的なメッセージが強いものが苦手なたちで、手塚先生の作品にもそういうものがあるんじゃないか、と思っていて、敬遠していた時期があったんです。子供のころや、学生のころにはあまり手に取らなかったですね。
初めて読んだときは、なんだか畏れ多くて、映像化するなんて考えはかけらも持たなかったので、気楽に手にとって読んだものです。まさか今になって、自分が手塚作品を映像化するとは夢にも思いませんでしたけれども。
キャラクターとしては親との思い出があって、僕が物心つく前に、母親が好きだったレオの帽子を毎日かぶっていたらしくて。その話はずっときかされていましたね。
——改めて、映像化しよう、という視線で「陽だまりの樹」を読んでみて、新発見した部分はありましたか?
藤尾:やはり、行き着く先に「夢」がある、というところが最大の魅力だと思うんですよね。若い頃は、そこまで読み込む力がなくて、もっと表面的なところで読んでいたのかもしれません。僕の年齢になってみて、いろんな経験をしてくると、手塚先生のおっしゃりたいことがより伝わります。
僕は、たとえ好きなものでも、客観的な立場に自分をおかないと、演出ができないんですよ。のめり込んでしまうととても偏ったものになってしまうので、一歩引いてみる感覚を大事にしています。
不思議なもので、あまり関心をもたないもののほうが、仕事が舞い込みやすい、というのもありますね。何年も「これがやりたい」と恋焦がれて、やりたいことをやりつくして映像をつくる、というのは、理想だと思うのですが、なかなかそういうものにめぐり合う機会って、そうそうないですよね。やりたくてもなかなかできなくもありますし。
●藤尾監督の撮影術
——成宮さんの証言では、藤尾監督はユーモアのある監督だ、ということですが。
藤尾:いや、たいしたことはしていないんですよ。たとえば、5話で、良庵が2年ぶりに江戸に帰ってくるシーンがあるんですが、舞台は三百坂なんですよ。……三百坂に帰ってきて、「2年ぶりか、懐かしいな」というようなセリフがあって。台本上はそれだけだし、そのまま撮るのはたやすいのですが、なにかやはり、良庵らしさを盛り込みたい。そのときに、あの、万二郎たちが毎朝駆け上っていた坂を、良庵自身も駆け上っていく、という発想に行き着くわけですよ。体が先に動くような感じで駆け上ろうとする良庵は、坂の途中で息が上がっちゃう。そこでたちどまって「あかん」と覚えた大阪弁でつぶやく、というようなシーンを撮ったのですが、成宮さんが言うのは、そういうネタのことなのかな、と思います。
——キャラクター作りに、いろいろな工夫をされている。
藤尾:できるでけ、一方向のみで見ないようにしているんですよ。広角にとらえて。演出は発想勝負というところがありますからね。走るシーンにしても、ぼくは陸上に興味があって、テレビのマラソン中継なんかも、食い入るように見るんですが、「ぼくは、走れる人がうらやましいんだよ」なんていう話を、成宮さんたちにすると、彼らも熱心に聞いてくれるんですよね。ありがたいことです(笑)。
よく、「虫の目」とか「鳥の目」とか言うじゃないですか。ディレクターは基本的に、「虫」でなければいけないと思うんです。キャストに近いところに入って、虫眼鏡で覗き込むように、細かいところにこだわって、突き詰めていく。でも、そればかりだと見ているお客さんが疲れる仕上がりになるんです。特にテレビはそれが顕著でして。
映画は、その世界に浸りたい人が、お金を払って見に行きますよね。でも、テレビは、ご飯を食べたり、子どもを抱っこしながら見たり、そういう視聴者が見ることを考えると、「虫」だけでは駄目なわけですよ。やはり、「鳥」の俯瞰で引いた感覚もあわせて、常に持っていないと。
——テレビドラマを撮られることが多いですか。たまに映画を撮りたくはなりませんか。
藤尾:もちろん、映画も撮ってみたい、とは思いますが、やっぱり、テレビがすきなんですよね。テレビばっかり見て、時代劇もよく見ていましたし。テレビの短さもまた、捨てがたいですよね。
映画のように、じっくりと時間をかけて撮る、というのもいいのですが、やっぱり、日本全国の方が見てくださっている、というのは感無量ですよね。
——最後に、ドラマ『陽だまりの樹』に込めたメッセージを、教えてください。
藤尾:自分らしさ、というのをみなさんにしっかり持っていてほしい、というのがぼくの裏テーマとしてありました。市原さんも成宮さんも、今、この時代・年齢で「陽だまりの樹」をやる意味に、ぼくはこだわっているんですよ。
これからもいろいろな役者さんたちが、万二郎を演じ、良庵を演じると思うのですが、誰がやっても同じではいけない。現場でも二人に散々言ったのが、「いま、このタイミングでやる意味を考えてほしい」と。
こういうと、変かもしれませんが、あえて未熟な部分を出してほしい、ということなんですよ。市原さんが30歳になったときに、この作品を見直して、「なんで俺、こんなことしてるんだ」というような感覚を持ってほしい。言ってみれば、記念写真みたいなもので、いまこの時代でしか撮れない二人を、ばんばん出してほしい、と思っています。
現場でも主役のお二人には、そんな話ばかりをしています。役作りの話は、言ってみれば原作を読み込んでもらえば良い話で、彼ら二人が、今なにが出来るか、ということのほうが重要だ、と思っています。私の役割としては、今の二人の良いところを、いかに引き出すか、ということですよね。
——お忙しい中、ありがとうございました。
BS時代劇『陽だまりの樹』、全12回の放送も残りわずかとなりました。 次回 第9回放送は6月1日予定です。




















