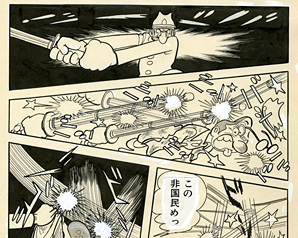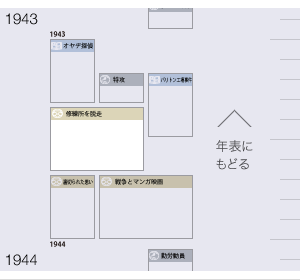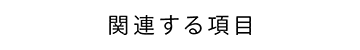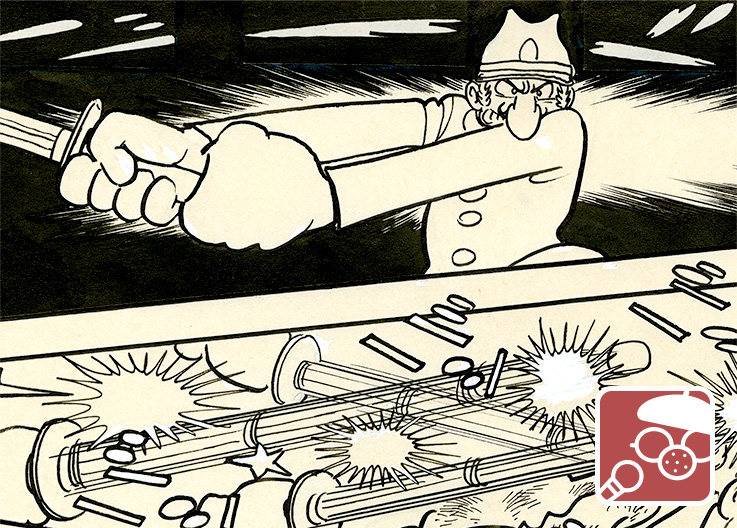修練所を脱走
1943-45年頃【14才~16才】
戦時中、軍の修練所で過酷な生活を強いられていた手塚治虫。飢えと暴力に耐えきれず命がけで脱走し、母のもとへと向かいました。
手塚治虫エッセイ集より
ぼくの中学校は大阪でも名門で、厳格さでも群を抜いていた。
太平洋戦争も酣(たけなわ)のころ、ぼくは強制的に予科練を受けさせられた。
ぼくは七つボタンにちっとも憧れたわけではないので、視力のために合格しなかったのはもっけの幸いであったが、途端に教官の一声で、強制修練所に入れられてしまった。
こうなると年貢のおさめ時で、漫画なんぞ描いていようものなら、それこそ非国民、反動扱いで拷問にでもあいそうな空気であった。
修練所のシゴキは凄かった。
畑仕事や教練はまあ我慢できるとしても、我慢ならないのはほとんど絶食に近いくらいの食事の減量だった。
目はおちくぼみ、腕は鳥の肢(あし)のようになり、ものを言う元気もなくなってきた。
教官だけは、どういうわけか丸々と肥え太り、元気旺盛(おうせい)だったので、隠匿品があるのだろうという噂がたち、とうとう教官室を襲撃しようかという計画まで企てた。

マンガ「紙の砦」原画より
しかし、これは実現しなかった。
ぼくは、こんな所から逃げだそうと思った。
しかし、修練所の周囲には鉄条網がはりめぐらされ、付近の地面は蟻が歩いても足跡がつくぐらいで、とても脱走はできない。
「だが、おれは脱走してみせる」と、ぼくは言った。
「ばか、日本刀で斬(き)られるぞ」
「このままいたって、どうせ餓死するだけだ」
ある夜、みんなが寝静まるのを待って、ぼくは修練所の窓から脱(ぬ)け出した。
ひんやりとした、おぼろ月夜だった。
ぼくは、あぶら汗を流しながら鉄条網をくぐり、足跡を消した。
草をかき分けて本道へ出ると、やっとシャバへ戻った安心感がこみあげてきた。
電車に乗って、ほうほうの体(てい)でうちまでたどりついた。
ふらりと玄関をはいると、出てきた母は、腰を抜かさんばかりに驚いた。
幽霊だと思ったそうである。
「腹がへった……」
と、一言いうと、ぼくはへなへなとすわりこんでしまった。
母は、家中から食べものという食べものを出してきて、ぼくに食わせてくれた。
ただもうありがたかった。
食料といえばとぼしい配給だけの時代だ。
おそらく、家中の食べものを洗いざらい食べてしまったに相違ない。
腹ができてホッと落ち着くと、また不安になってきた。
母は、修練所へ帰ったほうがよいという。
しかたなく、また電車に乗って、草深い鉄条網の中へ帰っていった。
なに食わぬ顔で寝てしまったので、誰にも気づかれずに済んだ。
講談社版手塚治虫漫画全集『手塚治虫エッセイ集 1』より
(初出:1969年毎日新聞社刊『ぼくはマンガ家』)

「手塚治虫の戦争体験」
収録日:1988/10/31
収録場所:豊中市立第三中学校