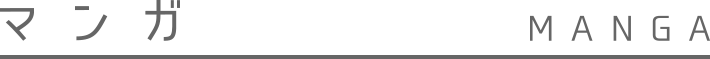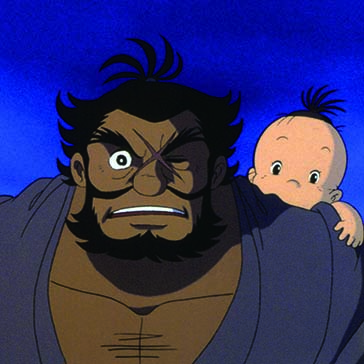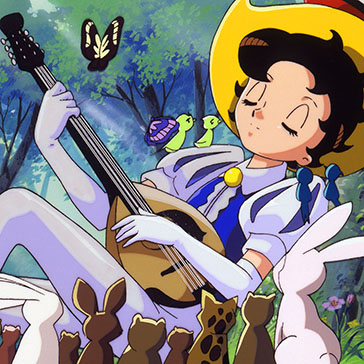ストーリー
ホラー映画のような大仰な始まり方もまた迫力がありますが、なぜか怪談というのはさりげなく語られれば語られるほど怖いものです。また、本や映画よりも、人の口から素朴に語られたもののほうが、怖さも倍増します。怪談は語りととても相性がいいのです。
この作品の手本となった中国清代の怪談集『聊斎志異』、また、日本の『耳袋』なども聞き書きの形をとっています。そのひそみに倣ったというこの作品もまた、手塚治虫自身が画面に登場し、ちょうど落語の「マクラ」のように成田空港のお稲荷さんに関する薀蓄を披露、なかなか本題に入りません。そこにある日手塚治虫を訪ねてきた女性が、「ぜひこれだけがお耳に入れたくて…」と言っておもむろに語りだし、やっと主軸の物語が始まる、といった形になっています。
とある大学の農学研究室。ある外国からの依頼によって、そこでは秘密裏に猛毒化学兵器の研究が進められていました。そこに動物園から、「毛並みが良くないから」と手放されてきたメスのキツネが実験動物としてやってきます。あたら殺されていった動物たちの恨みが立ち込めていそうで、ただでさえ不気味な農学研究室。そこにやってきた、古来よりよく化けて人心を惑わすというキツネ。これ以上ない道具立てです。
これが通り一遍の怪談ならば、化け狐が怖い、という話になりそうなものですが、そこは手塚治虫ならではのストーリー展開を見せます。実のところ、本当に恐ろしいのは化けも祟りもしない人間の大人たちだったりするところが、この作品のひねりの効いたところです。人間の恐ろしさがここにもまた、ものの見事にかき表されています。

解説
1971/05/23 「週刊少年キング」(少年画報社) 掲載