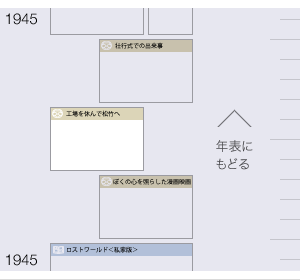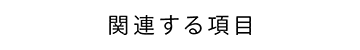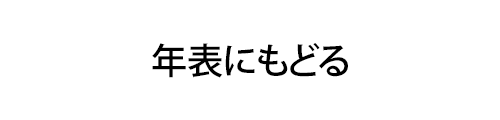工場を休んで松竹へ
1945年4月12日【16才】
映画「桃太郎 海の神兵」を松竹座で鑑賞しました。戦争映画でありながら平和的な描写や芸術的な演出に感動し、その完成度の高さを称賛しています。
1945年4月12日の日記より

大阪松竹座(現在も当時の姿で残っているが1994年に映画館から劇場へと改装された/2011年撮影)
四月十二日(木) 晴れ 暖かし
今日は工場を休んで松竹へ映画を見に行った。
「桃太郎 海の神兵」がどうにも見たくてたまらなかったのである。
向こうへついたら開演は十二時十五分で、まだ充分間があった。
初日というのに余りそう大して混んでいない。
歌劇を見るのが目的か、女学生が非常に多い。
やがてニュースに続いてマンガが始まった。
まず第一に感じたことは、この映画が文化映画的要素を多分に取り入れて、戦争物とは言いながら、実に平和な形式をとっている事である。
熊が小鳥を籠から出して餌をやり、或(ある)いはてるてる坊主や風鈴が風に揺られている所など、あくどい面白さの合間合間に挟まれて何か観衆をホッとさせるものがあった。
次に感じたことは、マンガが非常に芸術映画化されたことである。
即ち、実写のように、物体をあらゆる角度から描(えが)いてある。
例えば、猿や犬が谷川に飛び込む所なぞ真に迫っていた。
また映画の筋もこれまでになく判(はっ)きりとしていて、マンガというよりも記録の一種であった。
この映画が非常に長いのには舌を巻いた。
始め、また二、三巻のしよーもないものであろうと思ってたかをくくっていたのであるが、見てみると、九巻一時間十五分、普通の映画よりも長い位である。
これは現在までの最長篇のマンガであろう。
松竹もえらいものをつくったものだ。
大東亜の動物も大分出て来ている。日本語学校の所なぞ特に面白い。
私が特に感心したのは、口の動きがトーキーとよく合っている事と、実際の動作とよく合っている事だ。
これは、帽子が渓流を流れる時、熊や桃太郎が手袋をとる動作、飛行機内での所作(しょさ)などで肯(うなず)ける。
映画中に見事な影絵を入れたのも面白いし、また私は天狗猿と手長猿と眼鏡猿が、三匹でコーラスをやるのがとても気に入った。
講談社版手塚治虫漫画全集『手塚治虫エッセイ集 6』「思い出の日記——昭和二十年——」より