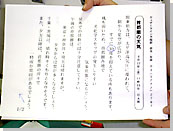|
 ↑今年の台風10号の写真。 かなり大きく、勢力が強いことが うかがえます。 |
さまざま雑多な書類が貼られた壁の向こうには、予報士さん達の机が並んでいます。 ここでは実際の予報を組み立てたり、ラジオやテレビで読むニュースの原稿を書いたりしています。気象庁からのデータの他に、ファックスなどで来る天気図や、時には実際の雲の様子を肉眼で見て予報を組み立てるそうです。 「私達にも雲の様子を見て天気が分かるようになりますか?」 「うーん…かなりの経験をつまないと難しいですね」 との事。そう簡単にはいきません。 「この映像は先週末(※8月16日あたり)日本に接近した台風10号の写真です。台風の目がはっきり写っているのが分かりますか?」 |
「地球の自転が影響しています。洗面所で水を流すと自然に渦になりますね。あれと同じです。夏のような暑い日、空気が暖められてふくらみ、軽くなって空に昇っていきます。温められた空気がどんどん昇っていくと、ちょうどストローで水を吸ったときのように、周りの空気がどんどん流れ込んできます。こうして大量の空気が空に昇って行くときにウズを巻き、ものすごい風になります。これが台風ですね。それが上空の冷たい空気で冷やされ、雲になるのです」 竜巻は台風の小規模なもの。小規模とはいえ、台風のように予報も出来ない上、風の巻く力も凄いので、侮れません。アメリカではそれこそ「オズの魔法使い」のように、家ごと吹き飛ばされるケースも少なくないとか。 「台風のときもものすごい分厚い雲がレーダーに移りますが、竜巻も入道雲の下で起こることが多いのです。あまりに大きい入道雲には気をつけてくださいね」 また、入道雲の下では雷も多いそうです。夏の風物詩の入道雲を近くで見かけたら、雷や竜巻にご注意下さい! |
 |
壁には12時間ごとの天気予想図が貼ってあります。 |
 |
会社内で予報を撮影することも可能です。
ニュースなどで読み上げる天気予報の原稿。こんな感じで読みやすいように大きな文字で書かれています。 |
 |
今のような天気予報はいつごろ始まったのでしょうか。 「これは明治時代、日本で始めて書かれた天気図です。およそ120年前のものです。今の天気図と比べてみてください。低気圧と高気圧の大まかな位置しか分からないようなものでした。現在の天気図はここまで複雑になっています」 並べて見せていただいた現在の天気図には、前線や細かい気圧配置、風の向きを表す記号などがきっちりと書き込まれています。 「これによって、今ではとても細かい予報が出せるようになりました」 ウェザーラインの提供するiモードサイト、「ブラック・ジャックのお天気ドクター」でも地域のとても細かいところの天気を予想してくれる「スポットde天気」などが便利ですよね。 |
最後に、今回ご案内していただいた気象予報士の吉田さんに、色々質問してみました! また、実際にテレビやラジオで流れる天気予報を作るには、予報士の資格のほかに、気象庁の発行する免許を取る必要もあります。免許は、主に、気象庁のデータを受信することができる設備があるかどうかなど、予報に不足のないデータを集められるかどうかを審査して決定されます。データを集めるには、とてもたくさんの機械が必要なので、個人ではこの免許を取るのは難しく、ほとんどの予報士が会社や放送局など、大掛かりな設備をおくことができる組織に所属しています。 案内していただいた気象予報士の吉田さん、今日は大変ありがとうございました! |
現代社会を支える天気予報は、今やテレビやラジオはもちろん、インターネットやiモードでも大活躍しています。あの天気予報が作られる現場、少しでも雰囲気が伝わったでしょうか? 皆さんも時には空を見上げて、雲や風の動きをよく見てみましょう。天気予報は出来なくても、何か新しい発見があるかもしれませんよ。 今回お邪魔した株式会社 ウェザーラインのページはこちら。 今回の社会見学に一緒に行った、キッズ@niftyのページはこちら。 |