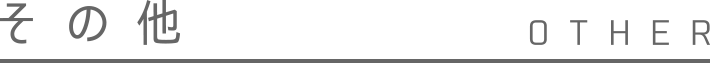内容紹介
小松左京 「宇宙は笑う」
日本SF界の大御所、小松左京とSFマンガのパイオニアである手塚治虫、この両氏がアポロの月面着陸について語る、というとロマンと科学と宇宙へのはるかな夢が語られていそうなものですが、火星にタコを送り込んでNASAを驚かせようとか、ロケットの中で味噌汁を食べたいとか、金星にサウナを作ろうとか芸者を上げようとか、もうとことん庶民的な、まるでどこかの居酒屋でダボラを飛ばしている酔っ払いみたいな話に終始するところが、なんとも楽しい対談です。
北 杜夫 「女は突然変身する」
そううつ病患者であることを自認している小説家の北杜夫氏は大のマンガ好きで昆虫採取を趣味にしていることでも有名です。そんな、趣味が合う男同士として、気の置けないなごやかな対談が進んで行きます。話題は昆虫のこと、そして昆虫の世界でのメスの役割から人間の女性についてと、発展して行きます。女は結局、異生物だと男ふたりがしみじみとうなずき会う。これはそういう対談です。
田河水泡 「のらくろとアトム」
大先輩の田河水泡に後輩手塚治虫がお話をうかがう、というスタンスの対談です。名作『のらくろ』以前に田河が人造人間、つまりロボットを主人公にしたマンガを書いていた、という話などとても興味深いことと思います。田河先輩の国民的人気マンガ『のらくろ』に比べれば自分のアトムなど、きわもの、にすぎないと謙遜するあたり、手塚治虫の先輩に対する真摯な気持ちが伝わってきます。
横尾忠則 「宇宙意識の目覚め」
宇宙意識とコンタクトをとりながら、前衛的な絵画を描きつづけていると語る横尾忠則氏と、宇宙意識の化身とも言うべき『火の鳥』をライフワークとしている手塚治虫との対談ですから、当然、宇宙的視野に立ったスケールの大きな対談が展開されて行きます。世紀末思想とは何か、からはじまり仏教感、ヨガ、宇宙人との精神的なコンタクトというふうに展開する対談は、そのまま「宇宙意識」から読者へと送られたメッセージ、というふうにすら思えてきます。
ジュディ・オング 「マンガは反逆のメッセージ」
手塚マンガはヒューマニズムにあふれているけれど、最近のほかのマンガは眉をひそめるようなものが多い、と語る歌手のジュディ・オングに対し、手塚治虫は「いや、自分のマンガは決してヒューマニズムを描いているのではありません。そもそもマンガというのは、すべて反体制的なものなんです」と応じます。自分のマンガも当初、当時のマンガ状況に対するアンチテーゼだったし、マンガではじめてキスシーンを書いたりしたときはものすごい非難を浴びた。自分はいつもアウトサイダーだった。手塚治虫はヒューマニズムにあふれた作品を描いてきたのではなく、常にいまの現実をマンガを通して告発してきたのだ、と自負していることが読み取れる、そんな対談です。
尾崎秀樹 「いまコミックに何を求めるか」
下品でパワフルでモラルの破壊を追い求めている人気マンガ『がきデカ』が大ブームになっていた当時のマンガ状況について語られている対談です。手塚治虫は『がきデカ』を抑圧された庶民の怒りのパワーの現れだと分析します。管理社会へとなだれ込んで行きそうな社会風潮に対する痛烈な異議申立てだ、と。そしてそういうマンガの持つエネルギーに手塚治虫は大いに期待しています。
磯村尚徳 「鉄腕アトムの家庭教育」
NHKキャスター、磯村尚徳氏はアメリカでのアトム人気について語り、世界に通じるマンガこそが文化となりうる、というようなことを語り、手塚治虫も世界の人が共通に理解できる作品作りを目指していると応じます。どんな国の子供たちでも目を輝かせて楽しむことのできる、マンガというのはそういうものでなければならない、と。
石ノ森章太郎 松本零士 「アニメ映画と心中する」
気心のしれたマンガ界の第一人者たちが語りあっています。けれど話題はマンガのことではなく、SF映画の話です。『スターウォーズ帝国の逆襲』にときめいたこと。ディズニーの『ブラック・ホール』がなんだかヘンテコだったこと、そして手塚治虫大絶賛の『ウォーター・シップダウンのウサギたち』と『ネオ・ファンタジア』のこと。原作を提供しているだけの松本氏と石ノ森氏に対し、原画から動画までせっせと書いている手塚治虫は「もっともっとアニメを作ろう」とはっぱをかけているのが面白い対談です。そんな手塚治虫の情熱に押されて、ついに松本氏は「心中しても本望と思えるようなアニメを作りたい」と言いますが、手塚は「なら早く作れ」とさらにせかすのです。
解説
(本書は潮出版社より刊行された『虫られっ話』(1981年)をもとに再編纂されたものです)