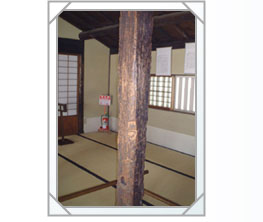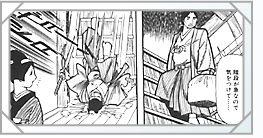|


 ↑今回お話を伺った米田該典先生 ↑今回お話を伺った米田該典先生


↑客座敷からの写真。
書斎の丸い窓が見えます。

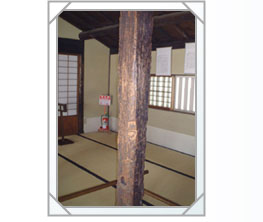
 |

↑塾生大部屋にある、作中にも登場した傷だらけの柱。 |
 |

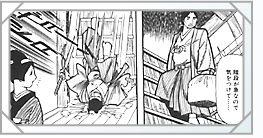

 |

↑急な階段には見学者のために手すりと滑り止めがつけられていました。良庵のように転ばなくてすむ!?
|
 |
|

手塚治虫や手塚作品のゆかりの地を訪ねるコーナー、「ゆかりの地見て歩き」第9回は、『陽だまりの樹』に登場する適塾を取材しました。
適塾は、正式名を「適々斎塾」といい、幕末の医人、緒方洪庵が開いた蘭学塾です。現在、重要文化財に指定され、ほとんど当時のままの状態で、大阪大学に大切に管理されています。今回の取材では、適塾や緒方洪庵の医術等に詳しい、大阪大学薬学博士・米田該典先生にお話を伺いました。
手塚良庵(後の良仙)が学んだ適塾の立つ大阪・北浜は、現在は企業のビルが点在する、静かなビジネス街といったところ。適塾は、近代的な高層ビルの間に、今も当時とほぼ同じたたずまいのままに残っています。
「大正時代の東西の軒切りで、建物全体が、当時よりほんの少し狭くなっているんですよ。…台所なんかも、多くの塾生の食事をまかなうにしては狭いでしょう?」
と米田先生がおっしゃる通り、確かに、台所は多くの塾生の食事を作るにしては少々手狭な感じがします。軒切りとは、大正時代に行われた、家屋などの軒を切って近代化に伴って行われた道路を拡張した作業のこと。これによって、敷地自体が少々狭くなってしまったので、間取りは少々変更されているとは言うものの、そのようにやむを得ない部分以外は、できる限り当時のままの姿に近づけて解体・修理したのが今の建物だそうです。
思ったより小ぢんまりとした門をくぐると、一階部分は主に教室や客間、適塾の主である洪庵が使用した書斎となっています。
「現在門は一つだけですが、当時の武士階級の常識から言っても、むさくるしい塾生と師である洪庵が同じ門から出入りしていたとは考えにくいですね。きっともう一つ門があったんだと思います」
落ち着いた雰囲気の書斎には、洪庵が使用していたと伝えられる使い込まれた薬品調合台も展示されていました。真摯に医学に取り組んでいた洪庵の人柄がしのばれます。
また、奥の蔵には、洪庵が使っていた薬箱が保存されているとか。今回は特別に、その薬箱も見せていただきました。
「薬箱は、当時の医者にとっては、一人前になって初めて持てるものでした。また、世襲されてゆくものではなく、あくまで一代限り、洪庵なら洪庵一人のみが使えるというものでした。だから外箱に家紋を入れたりはせず、持ち主の工夫が凝らされた機能的なものになっています。細工や装飾は凝っていて、かなりしっかりしたものになっています」
薬箱に入っていた薬を、米田先生自らが科学的に分析してみたところ、150年も前のものにも関わらず、多くの薬が新しい薬とほとんど違いがないほどに変質することもなく残っていた、とのこと。
「こんなに保存状態がいいのも、この薬箱のおかげでしょうね」
薬箱は外箱に覆われていて、それを取ると蓋付きの最上段にはガラス製の薬ビン、その下には3段の粉薬や丸薬を入れる引き出しがあり、写真の通り、薬は四角く箱状に折られた和紙の袋に丁寧に納められています。
「薬箱は木材でできていて、残っている薬は全て藍で染められた和紙の袋に入っています。和紙と木ですから通気性はとてもいいわけです。また、和紙を藍で染めることによって虫害も防止できますし、内箱と外箱で厳重にしまわれていましたから紫外線などによる変質もありません」
まさに先人の知恵の結晶といえそうです。
さらに上段にある薬瓶を見ると、
「このビンは普通のガラス瓶ではなくていわゆる硬質ガラスの瓶です。当時の日本にこういうものを作る技術があったんですね。蓋もすり合わせになっていて、現代我々が使用している薬品などを入れるガラス瓶と構造はほぼ同じです。おまけに瓶は四角くなっているので、中で転がったりすることもありません」
ここにも洪庵の医学に対する並々ならぬ研究心をうかがうことができます。

↑1階にある緒方洪庵の書斎。落ち着いた雰囲気です。 |
 |

↑洪庵が持ち歩いたくすり箱は、今でも現存しています。こちらは40歳ごろまで使用されたもの。
|
 |
|
 |
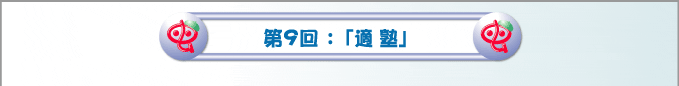

 ↑今回お話を伺った米田該典先生
↑今回お話を伺った米田該典先生